2025年「都道府県地価調査」(基準地価) つくば市の地価を支える基盤とは
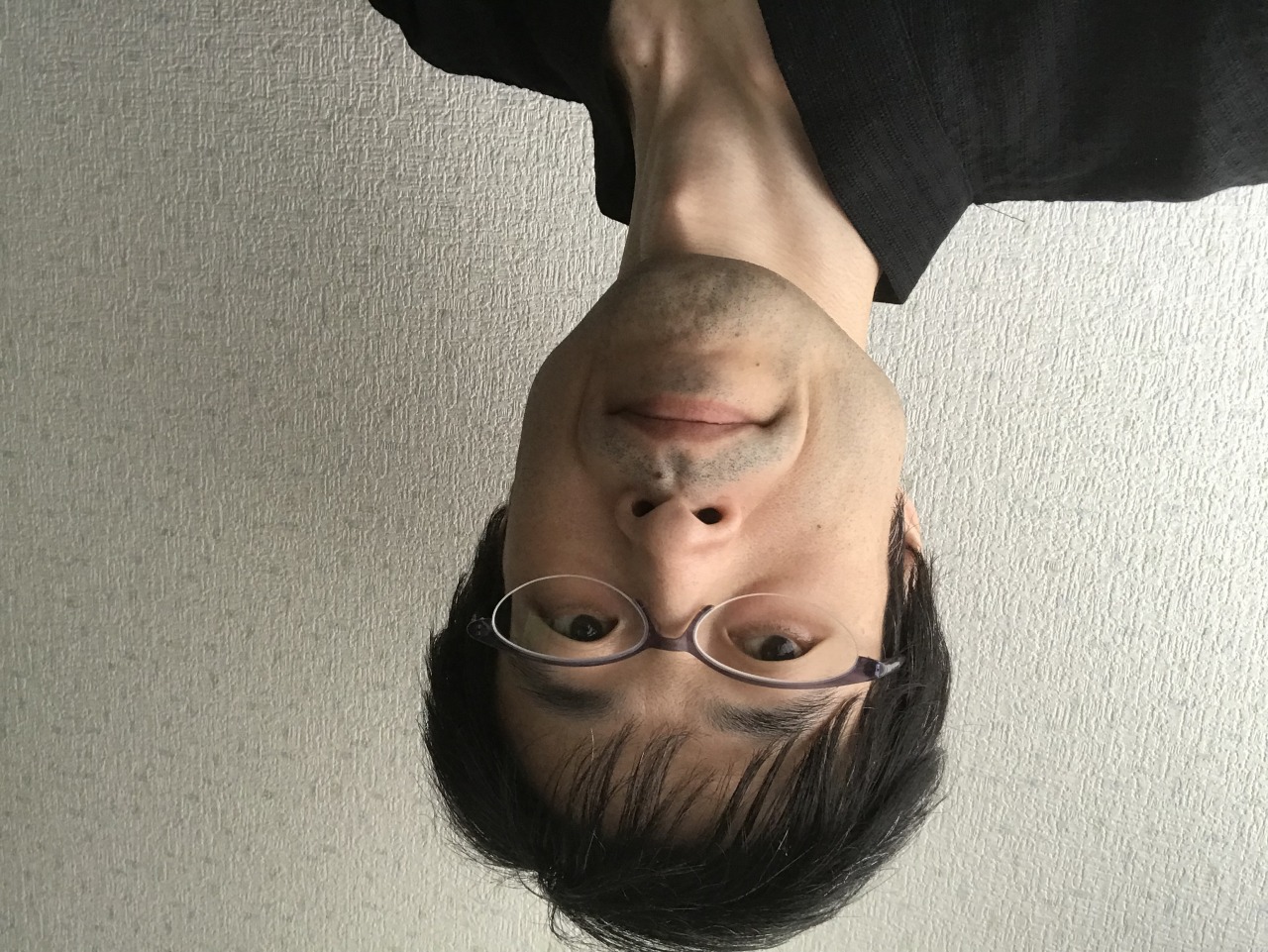
2025/09/21

全国「全用途・住宅地・商業地」いずれも4年連続の上昇
9月16日、国土交通省が「令和7年(2025)都道府県地価調査」の結果を公表している。「基準地価」の呼び名でも知られるものだ。いくつかトピックを挙げていきたい。
まずは、全国平均での変動率だ。全用途平均、住宅地、商業地のいずれも4年連続で上昇し、この間、上昇幅も拡大している。さらに、ひと足先に上昇が始まっていた工業地は8年連続となった。
| 年 | 全用途 | 住宅地 | 商業地 | 工業地 |
| 2025年 | +1.5% | +1.0% | +2.8% | +3.4% |
| 2024年 | +1.4% | +0.9% | +2.4% | +3.4% |
| 2023年 | +1.0% | +0.7% | +1.5% | +2.6% |
| 2022年 | +0.3% | +0.1% | +0.5% | +1.7% |
| 2021年 | △0.4% | △0.5% | △0.5% | +0.8% |
東京圏の地価上昇が加速
今回発表された数字のうち、注目されているひとつが東京圏での高い上昇率、および伸び幅となる。他の大都市圏と比べてみよう。(地方4市は、札幌・仙台・広島・福岡合わせての平均)
| 上昇率 | 上昇率(前年) | 伸び幅 | |
| 東京圏 | +5.3% | +4.6% | 0.7ポイント拡大 |
| 大阪圏 | +3.4% | +2.9% | 0.5ポイント拡大 |
| 名古屋圏 | +2.1% | +2.9% | 0.8ポイント縮小 |
| 地方4市 | +5.3% | +6.8% | 1.5ポイント縮小 |
このとおり、東京圏の数字が大きく、商業地では下記のとおりそれがさらに顕著になる。
| 上昇率 | 上昇率(前年) | 伸び幅 | |
| 東京圏 | +8.7% | +7.0% | 1.7ポイント拡大 |
| 大阪圏 | +6.4% | +6.0% | 0.4ポイント拡大 |
| 名古屋圏 | +2.8% | +3.8% | 1.0ポイント縮小 |
| 地方4市 | +7.3% | +8.7% | 1.4ポイント縮小 |
人口、人流が集中し、インバウンドも賑わう東京とその周辺。そこに集まる国内外からの投資マネー。周知のことながら、こうした状況が、上記の数字を生んでいる主な要因といえるだろう。
地価はバブルを目指すのか?
不動産投資マネー、地価上昇といえば、古い記憶をもつ世代はバブルという言葉をごく自然に思い浮かべる。
日本の地価は再びバブルを目指すのか? 以下、2つの数字を見比べてみよう。
都道府県地価調査における全用途・全国平均の変動率、および、消費者物価指数の全国平均・総合指数の変動率だ。
| 都道府県地価調査 | 消費者物価(前年平均) | |
| 1986年 | +2.7% | +2.0% |
| 1987年 | +9.7% | +0.6% |
| 1988年 | +7.4% | +0.1% |
| 1989年 | +7.2% | +0.7% |
| 1990年 | +13.7% | +2.3% |
| 1991年 | +3.1% | +3.1% |
| 1992年 | △3.8% | +3.3% |
| 都道府県地価調査 | 消費者物価(前年平均) | |
| 2021年 | △0.4% | 0.0% |
| 2022年 | +0.3% | △0.2% |
| 2023年 | +1.0% | +2.5% |
| 2024年 | +1.4% | +3.2% |
| 2025年 | +1.5% | +2.7% |
以上のとおり、バブル期の中心といえる頃においては、地価の高い数字と消費者物価の低い数字、各々の変動率には大きな乖離が見られた。すなわち、資産インフレが生じている。
一方、近年および現在においては、そうした状況は見られない。
目下、わが国の不動産を取り巻いては、大都市部でのマンション価格、インバウンド需要の集まるリゾート地での土地価格高騰といった、突出した事例はあるものの、全体としてバブルの時代とは大分様子が異なっている。
交通、子育て、教育環境の充実―――その効果めざましいつくば市の地価
今回の都道府県地価調査における地価上昇率の全国順位表(住宅地)を見てみよう。
1位は、北海道富良野市北の峰町の基準地、インバウンドに沸くスノーリゾートの中心だ。
次いで、半導体メーカー・ラピダスの工場稼働が話題となっている北海道千歳市の基準地。2位と3位に並んでいる。
さらに、4位はこちらも北海道、ニセコの山々に隣接する羊蹄山のふもと、リゾート地帯を望む真狩村。なお、真狩村の基準地は、もう1カ所が6位にも挙がっている。
そして、7、8、9位。北海道から遠く南下、宮古島など沖縄のリゾート地がここに連なるといった具合だ。
そのうえで、説明を飛ばした5位となる。
5位は、茨城県つくば市「みどりの東」にある基準地となっている。対前年変動率は+19.6%。
なお、同市「みどりの地区」といえば、教育関係に詳しい人など、「つくば市立みどりの学園義務教育学校」がある場所としてよくご存じだろう。小中一貫の公立校だ。2018年4月に開校。
研究学園都市・つくばという土壌を背景に、先進的ICT教育を実践するこの学校にあっては、近ごろ、子どもを入学させたいとして、学区への引っ越しを考える親御さんが多いとの報道も見られる。地元不動産会社への問合せもそれに伴い、増えているという。(なお「みどりの東」自体は同校の学区ではないので注意)
そこで、茨城県内における今般都道府県地価調査・住宅地での上昇率を見てみよう。なんと、つくば市の基準地が、1位から3位および5位から14位までを埋め尽くす状態となっている。(このうち、2位のつくば市みどりの1丁目が、上記義務教育学校の学区。変動率+16.1%)
県のコメントを抜粋しよう。
「つくば市の上昇地点は、TX(つくばエクスプレス)沿線の区画整然とした住宅地域で大規模商業施設、各種店舗、小学校等に近く、住環境に優れていることにより県内外から土地需要を取り込んでいる」
さらに、国交省のコメントだ。
「(つくば市では)保育施設の充実が図られ、令和6年4月には待機児童数0人を達成、地域子育て支援拠点の整備や子育てサポートサービスなどの子育て支援制度も整備され、令和5、7年では、全国の市の中で1位の人口増加率となるなど、子育て世代を中心に人口増加が続いている」
交通および生活の利便性、子育て・教育環境の充実。
これら、堅実に整備された地域の基盤が実需に反映し、それが地価を押し上げている様子のつくば市にあっては、バブルの萌芽と見紛うような要素は、現状見当たらないようだ。
地方圏(その他の地域)―――各用途から下落が無くなる
最後に。地方圏のうち「その他」の地域の数字となる(地方四市を除いた地方圏)。
今回、全用途、住宅地、商業地、工業地のいずれにも下落率が示されていない。29年続いた住宅地での下落がついに止まったためだ。
| 用途 | 変動率 | 前年 |
| 全用途 | +0.2% | +0.2% |
| 住宅地 | 0.0% | △0.1% |
| 商業地 | +0.6% | +0.5% |
| 工業地 | +2.2% | +2.3% |
ただし、都道府県別で見ると、住宅地の変動率がマイナスの道・県は今回26を数えている。47都道府県の半数を超える数字だ。さらに、横ばいは1県、変動率がプラスの都府県は20に留まっている。
以上、2025年「都道府県地価調査」の公表内容から、ほんのいくつかを紹介した。下記にて、さらに多くをご確認されたい。
(文/朝倉継道)
【関連記事】
地価LOOKレポート2025年第2四半期 中野のクールダウンと進撃のインバウンド
「税リーグ」と不思議な町おこし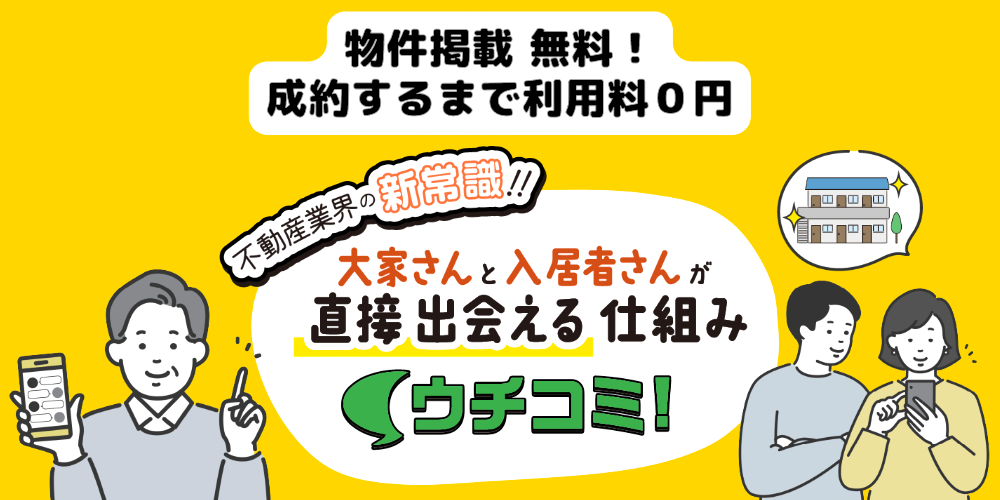
無料で使える空室対策♪ ウチコミ!無料会員登録はこちら
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。






















