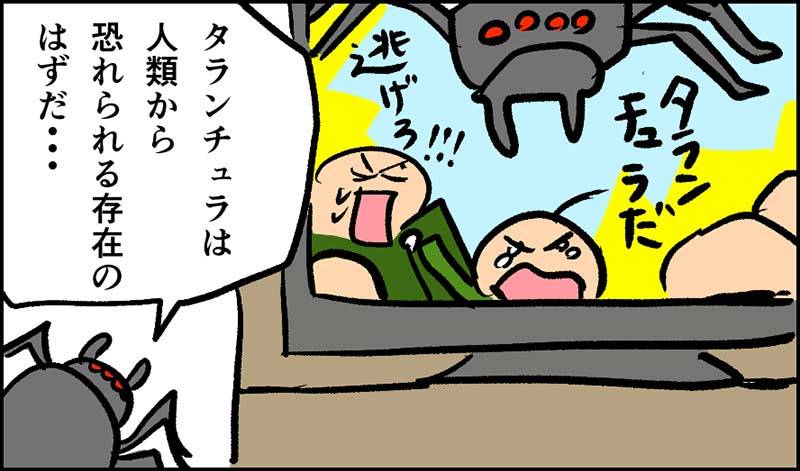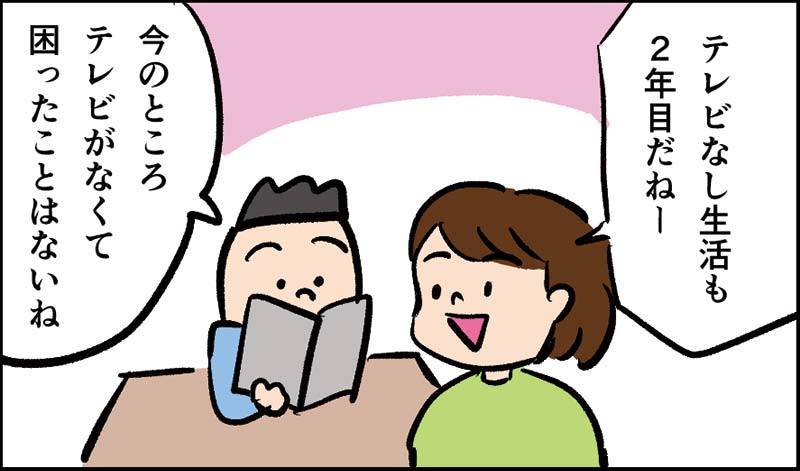持ち家に住んでいる人はより注意

2018/07/18

◆大筋の流れ
住んでいた持ち家には相続税が課税される。
まずは簡単だが、相続税全体の計算方法から説明すると、ざっくり下記の通りになっている。
① 亡くなった方が所有していた財産や借金の金額を全て合算
① ①の金額から基礎控除額(※1)を引く
① ②の金額を相続人全員が法定相続分(※2)で分けたものと仮定して、各相続人に金額を分ける
① 各相続人に分けた金額にそれぞれ相続税の税率(※3)をかける
① ④のそれぞれ税率を乗じた後の金額を相続人全員分合算する(納めるべき相続税の総額が確定)
① ⑤の合算された金額を各相続人が実際に財産を分けた割合の金額で按分する(それぞれが納めるべき相続税額が確定)
※1 基礎控除額
3,000万円+600万円×相続人の数
例)夫婦と子供2人で夫が亡くなった場合、
相続人の数は妻+子供2人で3人
※2 法定相続分
民法で決められた遺産の取り分
例)夫婦と子供2人で夫が亡くなった場合、
妻が全体の半分(1/2)
子供2人で残りを半分ずつ(このケースでは子供1人の相続分は全体の1/4)
※3 相続税の税率
10%~55% 財産の金額が多くなればなるほど、税率も上がっていく
亡くなった方が住んでいた家も①の財産の中に含まれる。
他に持っている財産と合算して計算されるが、戸建てでも分譲マンションでも土地+建物の価格をベースに相続税の計算を行う。
相続税の課税されるベースとなる金額は、市場で実際に取引されている価格とは異なり、税務上独自の評価を行う。
建物については固定資産税評価額がそのまま評価額となるが、土地については国税庁が出している路線価という道路につけられた金額や、固定資産税評価額を基に一定の倍率を乗じて計算する方法で評価する。
土地の場合、一般的には市場価格の8割程度の金額が評価額となることが多いといわれている。
(不動産鑑定士による評価によってもOK)
◆自宅土地の評価額は減らすことができる
亡くなった方が住んでいた自宅の敷地(戸建てでも分譲マンション等でもOK)については、通常通りの税務上の評価額から8割減らして相続税の計算を行うことができる。
最近の税制改正によって要件が細かくなってきているが、趣旨としては亡くなった方とその家族が住んでいた自宅を相続税の負担のために処分することを避けるために設けられている制度である。
この制度を「小規模宅地の特例」という。
基本的な考え方としては亡くなった方が、亡くなる直前まで住んでいた自宅の敷地であること、その敷地を取得した方が亡くなった方と直前まで一緒に住んでいた親族であるという条件を満たしていれば、この小規模宅地の特例を受けることができる。
ただし、形式的にこの条件で判断するだけというわけではなく、その敷地についても、その敷地を取得する親族についてもこの条件を満たしていなくても適用を受けることができる場合がある。
一部の例を紹介すると、
【自宅の敷地について亡くなる直前まで住んでいなかった場合】
要介護認定を受けるなどして老人ホーム等に入所している場合は、亡くなったときにはその自宅に住んでいなかったとしても、次の要件を満たしていればこの特例の適用を受けることができる。
・賃貸に出していないこと
・老人ホーム等に入所するまで別居していた親族を、入所後に住まわせていないこと
(元々一緒に住んでいた親族はOK)
・敷地を相続税の申告期限(亡くなってから10か月)まで持っていること
【敷地を取得した方が亡くなった方と直前まで一緒に住んでいた親族ではない場合】
敷地を亡くなった方と別居していた親族が取得した場合でも、次の要件を満たしていればこの特例の適用を受けることができる。
・敷地を取得した方が外国籍や外国に住所がないこと
・亡くなった方に配偶者がいないこと
・亡くなった方に同居していた親族(相続権がある方)がいないこと
・亡くなる日から3年以内に敷地を取得した方(その方の配偶者も含む)自身の持ち家に住んだことがないこと
・敷地を相続税の申告期限(亡くなってから10か月)まで持っていること
(これは俗にいう「家なき子」の取り扱いだ)
◆相続で取得した不動産を売却した場合
亡くなった方の自宅を相続した方がその自宅を売却した場合には、売却により生じた利益に対して所得税の負担が生じる。
所得税の計算は原則、全ての所得を合算して税率をかける方法(総合課税)をとっているが、土地建物の売却については他の所得とは切り離して別個で税率をかける方法(分離課税)となっている。
負担することとなる税額の計算は、
自宅の売却により生じた利益× ※税率(所得税15%+住民税5%の合計20%) (別途、復興特別所得税0.315%)
※税率は亡くなった方が自宅を手に入れた日から売却日の1/1までで5年超の場合を前提
となり、自宅の売却により生じた利益の計算方法は下記の通りとなっている。
売れた金額-(亡くなった方の購入金額+売却にかかった経費)
この式のうち、亡くなった方の購入金額については、
これらの特例が設けられており、
① 亡くなった方の購入金額がわからない場合…売れた金額の5%として計算できる
① 亡くなってから3年10か月以内に売却している場合…支払った相続税の一部を加算する(①と併用可能)
①については実際の購入価額がわかる場合でも有利な法で計算してよいことになっている。
そして、他にも税額を安く計算できる制度が設けられている。亡くなった方の自宅の利用状況に応じて使える制度が異なるため、それぞれ紹介すると、
【その自宅に引き続き住んでいた場合】
① 3,000万円の特別控除
上記の自宅の売却により生じた利益より3,000万円を控除できる
この規定の適用については所有期間に制限がない。
(買ったばかりで亡くなった場合でも適用できる)
ただし適用にあたり、前年及び前々年にこの規定の適用を受けていないこと等の要件がある。
① 軽減税率
上記の自宅の売却により生じた利益のうち、6000万円以下の部分が所得税10%、住民税4%、合計14%の税率で計算できる(別途、復興特別所得税0.21%)
(6000万円を超える部分は、所得税15%、住民税5%の合計20%)
(別途、復興特別所得税0.315%)
この規定の適用については、亡くなった方が自宅を持った日から売却した年の1/1までの期間が10年超の場合のみ適用できる。
また、①と併用が可能。
※上記①②の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けられなくなる。
適用を受けた年の翌年、翌々年まで住宅ローンを組んでも控除を受けられないため、
現状住宅ローン控除を受けている場合、これから受ける予定がある場合は上記とどちらの適用が得か注意が必要
① 買い換えの特例
相続した自宅を買い換えた場合には、課税を新マイホームの売却まで先送りにできる。
(売却代金より新居の購入代金の方が少ない場合は、一部は先送りされずに課税される)
この特例は売却する自宅に10年以上住んでいたこと、売却した年の前年~翌年の3年間の間に新マイホームを購入することなどの要件がある。
また、上記①②と併用できないため、どちらを選ぶか選択する必要がある。
【相続後その自宅が空き家となっていた場合】
3,000万円の特別控除(空き家に係る特例)
亡くなった日から3年目の年末までに亡くなった方の住んでいた自宅を売却した場合に、上記の自宅の売却により生じた利益より3,000万円を控除できる。
ただし、相続後住み続けている場合よりは厳しい要件が設けられており、その自宅については下記の要件を満たす必要がある。
・昭和56年5月31日以前に建築
・区分所有の建物(分譲マンションなど)でない
・亡くなる直前に一緒に住んでいた方がいない
・亡くなった時から何にも使用せず空き家であること
・基準に適合する耐震リフォームを施すor建物を取り壊して空き地であること
・売却金額が一億円を超えないこと
また、上記で紹介した亡くなった方の購入金額に相続税の一部を加算する規定についてはこの規定とは併用できず、軽減税率の規定も設けられていない。
この規定はいま問題になっている空き家対策で設けられているもののため、このような少し厳しい取り扱いになっている。
実際の使い勝手はあまりよくないかもしれないが、古い自宅を取り壊して土地を売却した時に優遇される措置があるくらいの認識を持っているとよい。
◆最後に
マイホームをお持ちの方が亡くなると、ご家族に相続税、そのマイホームを処分した場合は所得税の負担が生じることとなる。
マイホームそのものについては、下の世代への贈与で大きく優遇を受けられる措置は現状存在しないため、相続時に「小規模宅地の特例」を受けることが有利になることが多いと考えられる。
比較的地価の高い場所にマイホームを所有し、預貯金があまりない場合はご家族が自身の財布から税金を負担することになる。
また、すでに両親が老人ホーム等へ入所し、他の親族を住まわせている等の理由で小規模宅地の特例を受けられない状況にある人もいるのではないか。
筆者の親族もマイホーム(戸建て)から老人ホームへ入所し、別生計だった息子家族が元の家を取り壊し、自身で新居を建て直して住んでいる。
この状況では小規模宅地の特例は受けられないこととなっているため、同じような状況にある方、自身はどうか気になる方はとくに、その他の財産の状況と合わせてどのくらいの税負担になるか確認してみてほしい。
上記の説明に記載した条件は詳細なところまでは記載していないため、自身が当てはまりそうな場合は改めて専門家に相談してほしい。
納税が必要になりそうな場合、生前贈与や生命保険の加入、見直しなどで納税資金の確保のための対策を提案してもらうことが、ご家族に起こりうるトラブルを防止することになると思う。
この記事を書いた人
税理士
専門学校で簿記に触れ、税理士を志す。 平成25年より会計事務所に勤務し、平成28年税理士資格取得。 現在は会計事務所の所属税理士として勤務している。 人工知能に置き換えられない、提案型の税理士を目指し、 中小企業の顧問から資産税までさまざまな業務に携わっている。