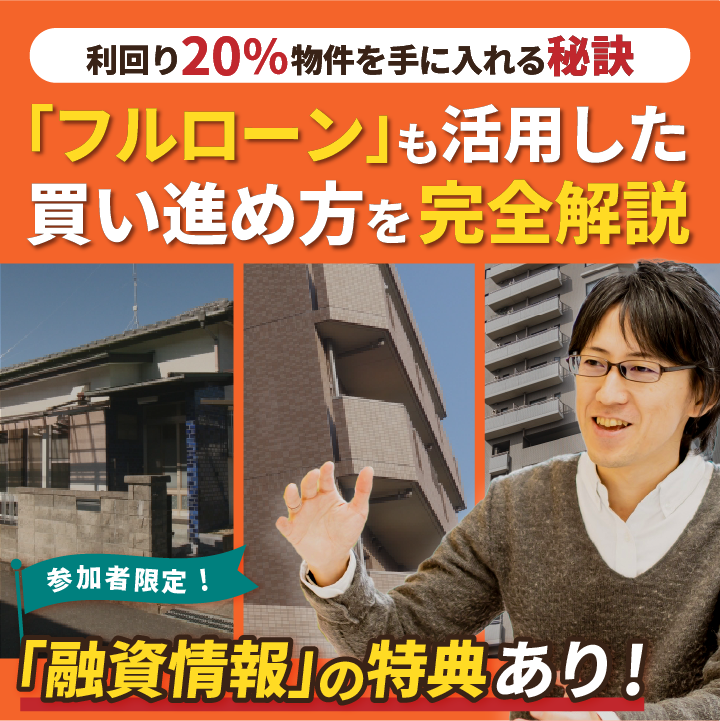民泊に逆風。投資の手段としての「弱点」が露わに?

2025/11/23

各地で民泊規制強化の動き
この秋、民泊への逆風が話題となっている。各地域の行政による規制強化の動きだ。自治体それぞれが随時定める取り決めや方針に翻弄されやすいという、投資の手段として考えた場合の民泊の「弱点」が、露わになっているともいえるだろう。
東京都豊島区や墨田区、大阪府、大阪府内の各自治体、軽井沢町といった名前がニュースに採り上げられているのを最近目にした人も多いはずだ。
さらに、規制の強化ではないが、新宿区ではこの9月に12の民泊事業者に対し、業務停止命令が下っている。都内では初のことだ。規制運用の厳格化を示すものといっていい。さらに、同区では11月にも9事業者に業務停止命令が出されている。
豊島区の厳しい条例改正案
こうしたうち、特に報道が目立つのが東京都豊島区での動きとなる。
同区では、9月9日に第1回目となる「豊島区住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会」が開かれた。以下2つを中心とした、新たな条例改正案がここで示された。
- 民泊の営業期間は、夏・冬休みに当たる年間84日間に制限する。既存の施設にも適用される
(7~8月、12月20日~1月10日に営業可) - 住居専用地域、文教地区での新設は認めない
(区内の約50%に相当するエリア)
なお、ここでいう民泊とは、住宅宿泊事業法による民泊をいう。年間180日までの営業が認められる、いわゆる「民泊」の中心となっているかたちを指す。
なので、上記のうち、前者の「年間84日間」は、すなわち現状の半分以下となる。まさに激減といっていい。
そのうえで、「既存の施設にも適用」というのがさらに厳しい。これら事業者にとっては、激震というべきものだろう。
そのため、これはもはや「財産権の侵害」―――などと、早速反対の声が挙がることになった。
そこで、区は、これら意見やパブリックコメントの結果も踏まえた上で、後日、修正案を提示している。上記2つについては、それぞれ以下のとおり手直しがされた。
- 民泊の営業期間は、春・夏・冬休みに当たる年間120日間に制限。既存の施設にも適用される
(3月15日~4月10日、7~8月、12月15日~1月14日に営業可) - 住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区での新設は認めない
(区内の約70%に相当するエリア)
見てのとおり、前案と比べると、前者では期間の制限がゆるくなっている(年間84日間 → 120日間)。ただし、既存の施設への遡及適用はそのままだ。
一方で、後者は強化された。住居地域、準工業地域が増えたことで、制限エリアが区内約50%から約70%へ拡大している。
なお、前者では、民泊運営のためすでにそれなりの投資をし、それが未回収となっているケースも多いであろう既存の事業者に対し、若干の配慮を加えた様子が見てとれる。
だが、後者は逆だ。いわゆる参入障壁がさらに大きく引き上げられている。
区による民泊への厳しい姿勢にあっては、今後も揺るぎない旨の意志が、これらに示されたと見ていいだろう。
以上、改正案は、11月12日から開かれる区議会定例会に諮られる。翌月の公告・施行を経て、区域と期間の制限については、来年12月の適用を目指すとのことだ。
規制強化に「理」あり?
さて、そんな豊島区だが、これまでは東京23区の中でも数少ない、民泊に対する独自の期間制限・区域制限をもたない区だった。いわば、民泊に優しいスタンスを採っていた。
それが、今回こうした動きに至った主な理由、それは住民からの苦情だ。上記、検討会の会議録冒頭にも、以下のとおり記されている。(抜粋・要約)
「現在、(豊島区での民泊)届出住宅数は1,700件を超えており、増加の一途」
「周辺住民からは、騒音、ゴミのポイ捨て、住宅前の喫煙、児童等への写真撮影や不用意な声かけなど、多数の苦情が寄せられている」
「区として、こうした生活環境の悪化が見受けられる状況を改善するため、条例改正による民泊実施の区域や期間の制限を設ける必要があると考える」
具体的な数字を挙げると、以下のとおりとなる。
| 1位 ゴミの取扱い | 35件 |
| 2位 騒音 | 33件 |
| 3位 タバコ | 29件 |
| 4位 標識の緊急連絡先が通じない | 16件 |
| 5位 管理会社に連絡が取れない | 14件 |
| 6位 標識が貼られていない、見づらい | 13件 |
| 全体 | 120件 |
とりわけ、トップ3に並ぶ「ゴミ」「騒音」「タバコ」については、通報に至っていない迷惑行為―――住民のストレスが、日常、相当数発生していることが想像される。よって、年間120件という数字にあっては、さほど大問題と感じられない向きもなかにはあるかもしれないが、現実はそうではないだろう。
さらに、以下の数字となる。
「豊島区88の町会長へのアンケート結果」(25年6月実施・一部を抜粋)
・「住宅宿泊事業施設(民泊施設)が町会内にでき、今までに困ったことはありますか?」
| ある | 64 |
| ない | 21 |
| 無回答 | 3 |
・「住宅宿泊事業施設(民泊施設)が町会内にできたことで、生活環境が悪化したと思われますか?」
| 悪化した | 55 |
| 悪化していない | 24 |
| 無回答 | 9 |
・「住宅宿泊事業法では、生活環境の悪化を防止するため、区域を定め期間を制限することができます。この制限は必要と考えますか?」
| 制限をかける(べき) | 78 |
| 必要ない | 5 |
| 無回答 | 5 |
現状「困ったことが起きていない」「生活環境が悪化していない」とする回答者にあっても、そうなる前の抑止の手段として、民泊への制限に期待する意思がつよいことが見てとれる結果となっている。
民泊施設が地域から迷惑施設と判断され、それに沿った厳しい対応を行政がとる場合、民泊を擁護する声はきわめて少なくなる可能性が、いずれの場所においても高そうだ。
民泊投資の基盤は脆弱
以上、冒頭にも述べたとおり、現在いくつかの地域で民泊への逆風が吹いている。
今後、しばらく続くと予想されるインバウンド(民泊需要の多くを占める顧客)の伸びを考えれば、これがさらに他地域へと広がっていく可能性ももちろん少なくないだろう。
投資としての民泊を考えたとき、その基盤はかなり脆弱だ。
各自治体による独自の規制やルールが、特に主流となる住宅宿泊事業法による民泊の場合、比較的簡単に布かれる構造になっている。なおかつ、その中には営業日数の制限といった、投資・事業としての民泊の死命を制する項目も存在している。
そのうえで、これに投資家が抗うのも難しい。
行政が民泊への規制を強める場合、通常、それを支えるのは、生活環境を守りたいという住民の「正しく」「切実な」声であるからだ。
このことは、他の投資に比べての民泊の大きな弱点、あるいは問題点として、常に意識しておくべきことだろう。
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
非弁行為と賃貸住宅管理会社 業界が抱く不安とは?
杉並区で擁壁が崩落。家がバラバラに。擁壁がある土地のデメリットに注意
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室