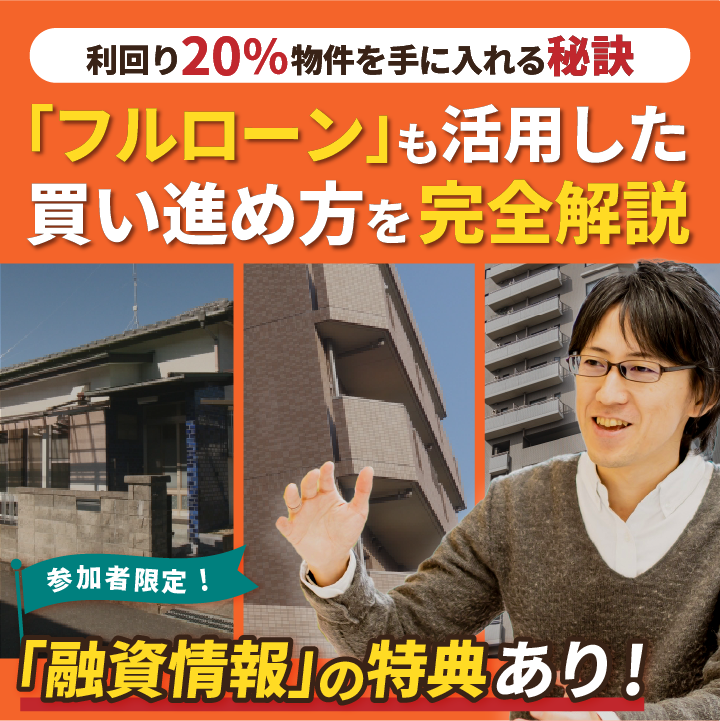低所得者層の背にのしかかる家賃上昇。24年度住宅市場動向調査

2025/08/20

国交省が「住宅市場動向調査」の結果を公表
この7月に、国土交通省が令和6年度(2024年度)「住宅市場動向調査」の結果を取りまとめ、公表している。01年度より続く調査で、今回で24回目となる。このうち「民間賃貸住宅に関する結果」部分から、いくつか目につくところをひろっていこう。
なお、調査の対象となっているのは、23年4月~24年3月の間に賃貸住宅(個人や民間企業が賃貸する目的で建築した住宅で社宅などを除く)に入居した、三大都市圏(首都圏・中京圏・近畿圏)在住の人々となる。回収された調査票の数は584となっている。
首都圏の範囲は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。中京圏は、愛知県、岐阜県、三重県。近畿圏は、大阪府、京都府、兵庫県。
物件を選ぶ際に妥協したもの―――家賃がトップ
住宅の選択理由―――いま住んでいる賃貸物件を選んだ理由の上位は、以下のとおりだ。複数回答においての割合10%以上となる1~7位までを抜粋する。
| 1位 | 家賃が適切だったから | 55.5% |
| 2位 | 住宅の立地環境が良かったから | 31.0% |
| 3位 | 交通の利便性が良かったから | 29.8% |
| 4位 | 住宅のデザイン・広さ・設備等が良かったから | 27.2% |
| 5位 | 職場から近かったから | 22.1% |
| 6位 | 昔から住んでいる地域だったから | 17.5% |
| 7位 | 親・子供などと同居した・または近くに住んでいたから | 15.4% |
このとおり、「家賃が適切だった」が、最も大きな割合を占めている。しかしながら、一方では下記のとおりともなる。
| 1位 | 家賃(予定より高くなった) | 27.2% |
| 2位 | 住宅の広さ | 19.5% |
| 3位 | 間取り、部屋数 | 17.5% |
| 4位 | 職場からの距離 | 14.7% |
| 5位 | 交通・生活利便性の高い立地 | 14.2% |
| 6位 | 台所の設備、広さ | 13.9% |
| 6位 | 浴室の設備、広さ | 13.9% |
| 8位 | 交通の利便性 | 13.4% |
賃貸物件選びにおいて、家賃の額が希望に適うことは多くの人にとって一番の条件だろう。だが、現実には、魅力的な物件を見せられたときなど、人々の心は動きやすい。上記は、実際の現場でよく見られるそんな風景を思い起こさせる結果ともいえそうだ。
いま住んでいる物件の家賃の分布
では、その家賃についての具体的な数字を覗いてみよう。まずは、いま住んでいる物件の月額家賃の区分別(5区分)の割合となる。
| 2.5万円未満 | 0.3% |
| 2.5万円以上5万円未満 | 17.0% |
| 5万円以上7.5万円未満 | 41.6% |
| 7.5万円以上10万円未満 | 20.6% |
| 10万円以上 | 20.5% |
加えて、
| 三大都市圏全体での平均月額家賃 | 77,677円 |
| 同じく中央値 | 70,000円 |
そのうえで、平均月額家賃においては3つの圏域における差が、以下のとおり大きい。
| 圏域 | 平均月額家賃 | 中央値 |
| 首都圏 | 82,967円 | 72,000円 |
| 中京圏 | 62,167円 | 60,000円 |
| 近畿圏 | 75,099円 | 70,000円 |
なおかつ、首都圏においては、上記のとおり中央値からの乖離が目立つ。これは、同エリアにおいて、飛び抜けて高額な家賃の物件が少なくないことを想像させるものとなる。(それらの数字によって平均値が引き上げられている)
住み替え前の家賃からの動き
以上を踏まえ、次に「住み替え前の家賃」を見てみたい。
| 2.5万円未満 | 3.0% |
| 2.5万円以上5万円未満 | 24.3% |
| 5万円以上7.5万円未満 | 33.8% |
| 7.5万円以上10万円未満 | 20.6% |
| 10万円以上 | 18.2% |
さらに、
| 圏域 | 平均月額家賃 | 中央値 |
| 三大都市圏全体 | 73,510円 | 65,000円 |
これをさきほどの「いま住んでいる物件」の数字と比べると、以下のような動きとなる。
| 家賃 | 住み替え前 | 住み替え後 | 備考 |
| 2.5万円未満 | 3.0% | 0.3% | 割合減少 |
| 2.5万円以上5万円未満 | 24.3% | 17.0% | 割合減少 |
| 5万円以上7.5万円未満 | 33.8% | 41.6% | 割合増加 |
| 7.5万円以上10万円未満 | 20.6% | 20.6% | 割合変わらず |
| 10万円以上 | 18.2% | 20.5% | 割合増加 |
| 三大都市圏全体での平均月額家賃 | 73,510円 | 77,677円 | |
| 同じく中央値 | 65,000円 | 70,000円 |
見てのとおりだ。
5万円未満までの低家賃では割合が減少。5万円以上の中程度~高額な家賃では増額傾向。すなわち、住み替え前から住み替え後にかけては、支払われている家賃が総じて増加している。
これらは、現下わが国において進行している物価上昇に付随しての家賃の上昇が、あらためて明確な数字となり、表れているものといえそうだ。
徐々に割合を増やす、賃貸に暮らす低所得者世帯
民間賃貸住宅入居世帯の「世帯年収」は、以下のとおりとなっている。
| 400万円未満 | 33.9% |
| 400万円以上600万円未満 | 23.6% |
| 600万円以上800万円未満 | 13.4% |
| 800万円以上1,000万円未満 | 7.5% |
| 1,000万円以上1,200万円未満 | 2.4% |
| 1,200万円以上1,500万円未満 | 1.0% |
| 1,500万円以上2,000万円未満 | 0.5% |
| 2,000万円以上 | 1.0% |
| 無回答 | 16.6% |
このうち、「400万円未満」の経年変化を見てみよう。
| 20年度 | 29.4% |
| 21年度 | 29.6% |
| 22年度 | 30.4% |
| 23年度 | 31.4% |
| 24年度 | 33.9% |
このとおり、少しずつ割合が増加している。
よって、単純にいえば、現在わが国の大都市部においては、
「家賃は全般的に上がっている」―――「しかしながら、賃貸に住む人のうち低収入の人の割合は増している」
これらが、徐々に進行しているものといえそうだ。
なお、各統計やそれを受けての報道等にも見られるとおり、今後の日本においては、いわゆる氷河期世代を中心として「持ち家が無い層―――持てなかった層」の高齢化が進んでいく。
よって、これら家を所有しない人たちの住宅確保にどう取り組んでいくかが、ゆるがせにできない課題となる。
家賃補助政策、あるいは税制などの再構築含め、国の知恵と力が試されるひとつといっていいだろう。
令和6年度(2024年度)「住宅市場動向調査」の結果については、下記で内容をご確認いただける。
「国土交通省 ~令和6年度住宅市場動向調査の結果をとりまとめ~」
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
家賃上昇の波高く、大学新入生市場は息切れ? 2025年前半・家賃の「いま」
賃貸・家賃を「値上げします」と言われたら
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室