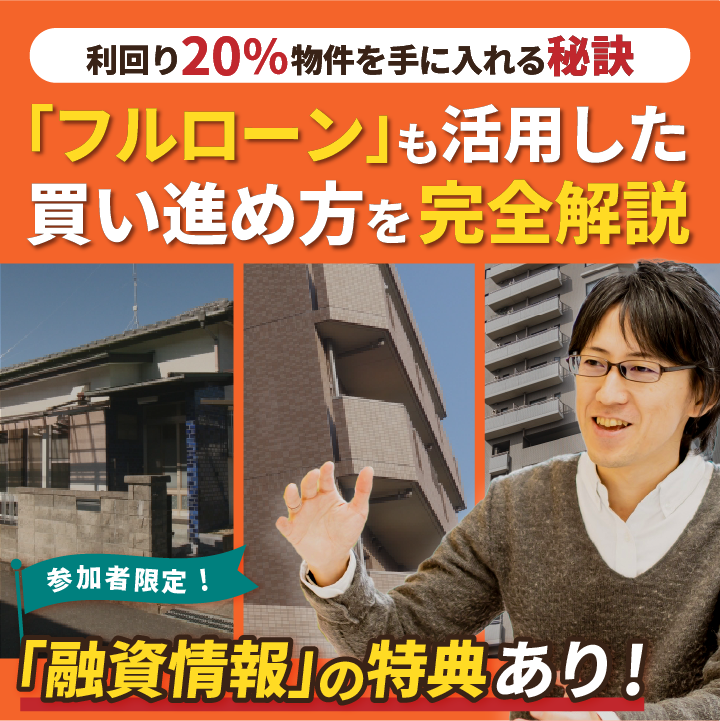不動産クラウドファンディングの押さえておきたいリスク

2025/10/05

ダイムラー・コーポレーションが破綻
今年7月、不動産関連の事業を行っていたある会社が倒産した。横浜市の(株)ダイムラー・コーポレーションだ。15日に、横浜地裁が破産手続きの開始を決定している。
同社は、不動産コンサルティングや賃貸管理などを手掛けるほか、不動産特定共同事業法に基づく「小規模不動産特定共同事業者」の登録も受けていた。これにより、不動産クラウドファンディング事業―――略して不動産クラファンを行っていた。
東京商工リサーチ(TSR)が7月22日に報じた破綻理由の一部を抜粋しよう。
「競合激化や市況変動などによって業況が悪化。計画通りに事業を進められず、赤字を計上したことで債務超過へ転落。経営不振が続くなか、2025年6月に社長が死去したことで事業継続が困難となり―――」
経営不振に至った具体的要因は詳らかでないものの、ともあれ、一般投資家から広く資金を募って運営する事業を行っていた会社が倒産したということで、本件は、不動産業界周りで今年起こった社会的事件のひとつに数えられるものとなっている。債権者約300名に対し、負債総額は約3億3000万円とのことだ。
不動産クラファン事業とは?
不動産クラファン事業者とは何か?
それは、広く出資を募って不動産の売買、賃貸等を行い、その収益を出資者すなわち投資家に分配する事業を行う事業者(※1)のうち、インターネット上で投資を勧誘する者をいう(※2)。
※1 不動産特定共同事業者および小規模不動産特定共同事業者
※2 または、勧誘を委託する者および、委託される者(クラウドファンディング業者)
つまりは、不動産の権利を小口化し、複数の投資家へ販売するビジネスだ。それをネットを介して行う。
これにより、通常、複雑な手間や時間を要しがちな不動産投資が、ネット上で手軽に手続きできる、便利な金融商品への投資に等しいものとなる。
1994年に制定された不動産特定共同事業法に、2013年、17年の改正法施行が加わり、さらに2019年、電子取引業務ガイドラインの適用が始まったことで、いわゆるネットビジネスとしての体制が確立された。
小口化された「ファンド」それぞれにつき、投資家は「1万円から~」といった小さな出資規模で、これに投資ができるものとなっている。
そのうえで、投資した物件からの賃貸収入(インカムゲイン)や、売却益(キャピタルゲイン)の分配を期待するかたちとなるわけだ。
押さえておきたいリスク
不動産クラファンの土台となっている不動産特定共同事業を行う事業者を管理する法令等の整備は、先ほども触れたとおり、すでに90年代半ばから始まっている。
その後も、特例事業とよばれるいわゆる倒産隔離のための仕組みが設けられたり、前述のとおり、電子取引のためのガイドラインが定められたりと、国は随時、投資家保護のための手当てを講じて来ている。
そのうえで、監督官庁である国土交通省は、今年も同趣旨に基づく検討会を重ねている。業界団体もこれに沿った動きを進めている(自主規制ルール等の検討)。こうした努力は、今後も課題があるごとに続けられていくだろう。
とはいえ、投資はやはり投資だ。不確定な将来に向かってお金を投じることへのリスクは決して切り離せるものではない。ましてや、その投資に対し、無知なままでの参入はいうまでもなく無謀なことだ。
そこで、以下では、大事なポイントをいくつか挙げていこう。これらは、不動産クラファンへの投資に臨むにあたり、そのリスクに関して知っておきたい基本となる。
以下を知っておけば、各事業者の掲げる募集案内等への理解がよりしやすくなるはずだ。
「不動産特定共同事業者」と「小規模不動産特定共同事業者」
まず押さえておきたいこと。
それは、不動産クラファンを行う事業者には、法律で定められた事業規模等の違いがあるということだ。
一方は「不動産特定共同事業者」となる。こちらは事業を行うにあたり、国からの「許可」を得ている。
一方は「小規模不動産特定共同事業者」となる。こちらは許可よりも参入のハードルが低い「登録」を受けて事業を行っている。
つまりは、より厳格な審査を通らなければならない許可業者である前者に比べ、後者は、かたちとしては(実質は別)信用度が下がることになるわけだ。
そのため、後者(小規模不動産特定共同事業者)に対しては、一般の投資家1人がその事業者に対して出資できる金額として100万円以下、1事業者が投資家から受けられる出資の総額が1億円以下という、不動産への投資を行う規模としてはかなり厳しめの制限が課されている。
逆にいえば、投資家の安全・保護のため、相当に低い位置でのキャップが設けられているということだ。
なお、冒頭のダイムラー・コーポレーションは、小規模不動産特定共同事業者だった。よって、今回の倒産により投資家が失ったであろう金額は、1人100万円を超えないものと見られている。つまり「キャップが効いた」ものと、一応いえるだろう。
利回りとリスクの関係(基本中の基本)
倒産したダイムラー・コーポレーションが募集していたファンドについて、投資家などからは「予定利回りの高いものが多かった」との声が挙がっている。事実であれば、投資の際に注視すべき基本的なリスクがそのまま顕在化したかたちとなっている。
不動産に限らず、あらゆる投資の世界において、ローリスク・ハイリターンは基本ありえない。高い利回りの裏側には、それなりのリスクが潜んでいるものだ。
「優先劣後」とは?
優先劣後―――この言葉と意味をしっかりと理解しておこう。
たとえば、ファンドの案内に「優先劣後構造あり・劣後出資割合20%」と表示されていたとする。これは、そのファンドに「優先劣後」の構造―――仕組みが設定されていることを示すものだ。
優先劣後は、投資家保護のため、多くのファンドで採用されている。この仕組みにおいては、事業者の出資分を「劣後出資」と呼ぶ。対して、投資家の出資分は「優先出資」だ。両方を合わせて出資総額がまかなわれるかたちとなっている。
そこで、たとえば上記のプロジェクト―――優先劣後構造あり・劣後出資割合20%―――が、期待どおりの結果を出せず、元本(総額)に毀損が生じた場合、その負担については総額の20%までを劣後出資している方が受け持つ。つまり事業者だ。毀損分が総額の15%ならば、その全額を事業者が被ることになる。投資家には負担が無い。
一方、20%を超える損失が出た場合は、投資家もその超えた分からは逃れられない。自らが出資した元本に毀損が及ぶ。すなわち、逆にいえば、そうした事態になるまで投資家は守られるわけだ。
よって、そのファンドに優先劣後構造が設定されているか、設定があるとして劣後出資割合は何%か―――は、投資のリスクを考えるにおいて大事な要素のひとつとなる。
元本割れのリスク(基本中の基本)
上記、優先劣後の仕組みは、不動産クラファンに元本割れのリスクがあるがゆえ、採用されるものだ。つまり、この投資は株などと同じだ。元本が保証されるものではない。
「倒産隔離」とは?
ファンドによっては、倒産隔離という、さらに投資家保護の効果が高いスキームが採用されているものもある。
これは、投資の対象となる物件の所有を特別目的会社(SPC)というものに委ねることにより、構築される仕組みだ。
倒産隔離が行われている場合、不動産クラファンを運営する事業者が倒産したとしても、物件は別の会社が保有している。そのため、債権者による差し押さえがそこまで及ばず、投資家は基本として影響を受けない。
よって、倒産隔離スキームが採用されているか否かもまた、投資の判断材料のひとつになる。
借入れがある場合のリスク
ファンドによっては、投資家や事業者の出資に加え、金融機関からの借入金も合わせた上で、より高額な投資を行うものもある。投資家の立場からは、いわゆるレバレッジが効くことになるため(出資の額に比べて運用規模が大きい)、リターンがさらに有利となるかたちだ。
ただし、当然ながら、期待どおりの物件運営(賃料収入)や売却が実現されなかった場合、金融機関への返済や利息の支払いに取られるかたちで、配当が減ったり、元本に毀損が生じたりといった状況が起こりうる。
よって、そのファンドが「借入れ」ありのプロジェクトか否かも、やはり大事な判断材料になってくる。
その他、不動産投資としてあたりまえのリスク
不動産クラファンは、まさにネットで金融商品を購入するのに等しい手軽さで、不動産投資が可能となる便利なものだ。
しかしながら、そこで集めた資金を使い、現場で行われることは、あくまで面倒なことだらけの不動産投資であり、不動産経営そのものとなる。よって、そこには投資の成功・不成功を左右する色々な要素が絡んでくる。
そうした「あたりまえ」のリスクもしっかりと心得ておこう。
- 物件価格の下落、売却の遅れ
……時々の経済情勢や、国の政策・税制・規制、金利の変動、事件・事故、自然災害など、実にさまざまな要因によって、これらが起こりうる。 - プロジェクトが期待通りに進まず、収益に影響が及ぶ
……各種法的手続きが難航したり、建設・リフォーム工事が人員や資材の不足、その他のトラブル等によって遅延に陥ったり、といったことが起こりうる。 - 物件運営が上手くいかない
……たとえば、予定されていた賃料が確保できないといった状況にあっては、事業者側の努力によってもコントロールし得ない賃借人(テナント)側の事情が絡んで来ることもある。 - 不動産クラファン事業者の倒産リスク
……これが現実化したのが、本記事冒頭に挙げた事例となる。
以上、不動産クラファンへの投資に臨むにあたり、そのリスクに関して知っておきたい基本を並べてみた。
最後に、まだ若くして亡くなったダイムラー・コーポレーション代表取締役の冥福を祈りつつ、本記事を終えることとしたい。
(文/賃貸幸せラボラトリー)
【関連記事】
大麻密売グループと仲介会社スタッフが管理会社を騙した! 罰則が強化されている大麻事犯
2025年「都道府県地価調査」(基準地価) つくば市の地価を支える基盤とは
仲介手数料無料の「ウチコミ!」
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室