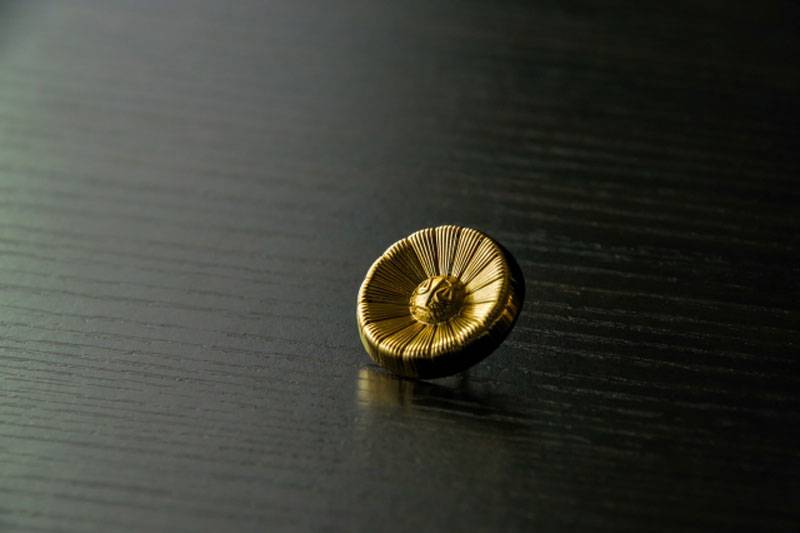特別受益と遺言証書のポイント

2019/02/20

イメージ/123RF
「夫から居住用マンションをもらっていたのに、何で、夫が死んだあとに売らなきゃいけないの?」
もしかすると、こんな体験をされた方がいらっしゃるかもしれません。
今回は、夫からマンションを生前贈与されていたのに、遺産分割の結果として、マンションを売却せざるを得なくなるケース及び改正民法903条4項(特別受益の持戻し免除の意思表示の推定)並びに改正民法968条2項(自筆証書遺言の方式の緩和)について説明していきましょう。
1 生前贈与されたマンションを売らなくてはならない理由
夫と妻は、婚姻後、30年以上、夫の所有するマンションで生活していました。夫には連れ子が一人いましたが、妻とは関係が良くなく、20年以上、交流はありませんでした。
夫は、妻に対し、「自分が死んだ後は、このマンションに住み続けて欲しい」と述べ、3000万円相当のマンションを生前贈与しました。
その直後、夫は交通事故で即死しました。
夫は、遺言書を残していませんでした。
夫の財産としては、預貯金1000万円だけ残っています。
この事例の場合、夫の相続人は、妻と、夫の子の2名です。
死亡時の夫の財産は、預貯金1000万円だけですが、遺産分割の際、夫の妻に対する3000万円相当のマンションの生前贈与は、特別受益に該当するため、相続財産に持戻して計算されます。
すなわち、法定相続分に従うと、4000万円(預貯金1000万円+マンション3000万円)を、妻2分の1、夫の子2分の1で分割することになるため、それぞれ、2000万円ずつ、遺産を分けてもらえるということになります。
しかし、預貯金は1000万円しかありませんから、3000万円相当のマンションをもらっている妻は、夫の子に対し、1000万円の金銭を支払う必要があり、これを調達することができない場合には、マンションを売却せざるを得ないこともあります。
そこで、従来は、持戻し免除条項のある遺言書を、夫にあらかじめ作成しておいてもらい、妻にマンションが残るよう対処していました。
具体的には、マンションについて持戻し免除の条項を入れるとともに、夫の子の遺留分に配慮し、預貯金を夫の子に相続させる等です。
2 改正民法903条4項(特別受益の持戻し免除の意思表示の推定)
今般、相続法改正により、次の条項が新設されます。
「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定(特別受益の持戻し)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」
これによれば、持戻し免除条項を入れた遺言等が存在していなかったとしても、①婚姻期間20年以上の夫婦であり、②居住の用に供する建物又はその敷地の遺贈又は贈与である場合には、持戻し免除の意思表示の推定が及ぶことになります。
すなわち、今後は、本件のケースのように持戻しを免除する旨の遺言がなかった場合であっても、夫の妻に対するマンションの贈与について、夫には持戻し免除の意思表示が存在するものと推定されることになり、これが反証により覆らない限り、マンション相当額はみなし相続財産の範囲に含まれないことになります。
とはいえ、改正法施行期日以前になされた贈与、遺贈については適用されない、遺贈の場合の持戻し免除は遺言によってなすべきとの考えもあるため、念のため、遺言を作成し、持戻し免除条項を挿入しておくべきです。
3 改正案968条2項(自筆証書遺言の方式の緩和)について
なお、2019年1月13日、自筆証書遺言に関し、次の改正が施行されました。
「前項の規定(自筆証書遺言の要件)にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。」
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。誰にも知られず、簡単に遺言書を作成することができ、費用もかかりません。ただ、方式不備で無効とされる危険性が高く、偽造・変造される危険性も大きいものです。
この改正によれば、今後は、多数の不動産や預貯金が存する場合に、いちいち全部について自書しなくとも、目録をパソコンで作成したり、全部事項証明書や預金通帳のコピーを目録として使用することができることになります(ただし、署名押印が必要)。
もっとも、目録部分の加除訂正の方法については改正されておらず、従前と同様の方法により加除訂正をする必要があるため、注意が必要です。
この記事を書いた人
弁護士
弁護士。1976年生まれ、東京都出身。 明治高校、明治大学、獨協法科大学院 卒業/都内法律事務所を経て、佐久間法律事務所所属。取り扱い案件は、保険法関係、知的財産関係、介護相続関係など。モットーは「トラブルの火種は放置せずに事前対策と早期対応」