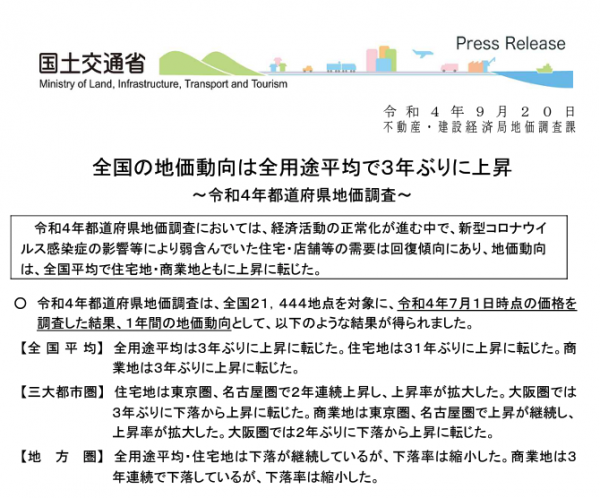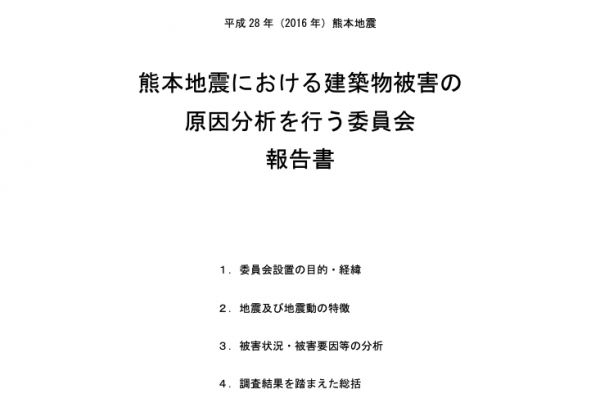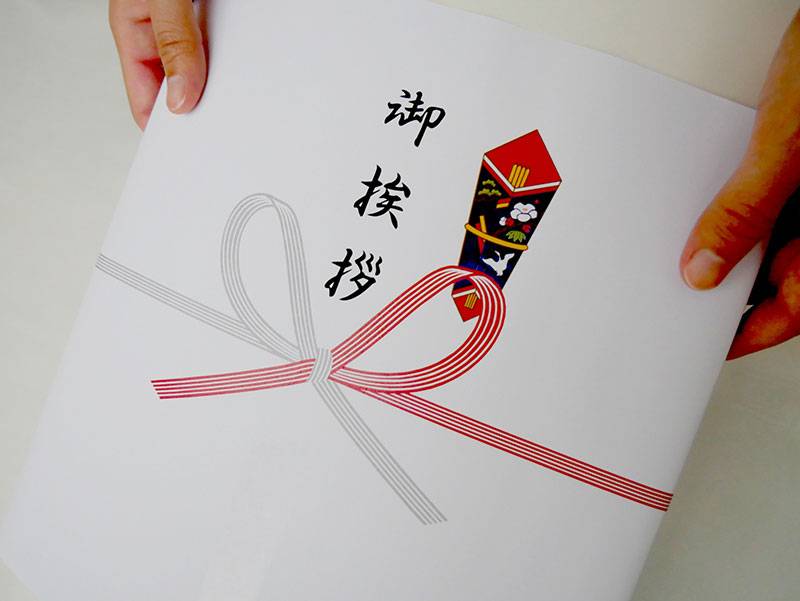これからの街づくりと待ったなしの“老朽化マンション”再生問題

2021/10/13
前編(新たな住宅セーフティネット制度の驚くべき現状と子育て世帯への支援制度)に続き「これからの街づくりと建物再生」についてお届けする。
令和時代の住宅政策の指針となる『住生活基本計画』
国土交通省から2021年3月に発表された、『住生活基本計画』。令和3年度~令和12年度の10年間に及ぶ我が国の住宅政策の方向性を示す大変重要な指針だ。
住生活を巡る現状と課題に対応するため、3つの視点から8つの目標が設定されている。

出典/国土交通省「新たな住生活基本計画の概要」を基に作成
“いま”の住生活を巡る現状と課題が明確になるこの計画だが、そのなかでもコロナによる賃貸業界の変化や空き家問題は、賃貸住宅オーナーにとっても注目に値する話題である。
こんな話題もあった。コロナ禍により、働き方が変わったことで家賃が高く狭い都市部に住む必要がなくなり地方移住が増えるのではないかと。実際はどうなのだろうか。
東京圏の転入超過数の推移(2014年度~2020年度)

出典/総務省統計局「東京都の転入超過数(2014〜2020)」を基に作成
東京都からの転出者数の前年度差(道府県、2020年度)

出典/総務省統計局「新型コロナウイルス感染症の流行と2020年度の国内移動者数の状況」を基に作成
東京都の転入超過数が大きく縮小し、東京都からの転出者数は近隣の県を中心に増加していることがデータに表れているが、国土交通省国土技術政策総合研究所 建築研究部長・長谷川洋 (はせがわひろし)氏は、「実際にコロナの影響で大きく移住が行われているかどうかについては、さまざまな調査結果やデータも示されつつありますが、きちんと分析する必要があると思っています」と慎重だ。
東京一極集中の流れが今後どうなるかは、さらなるDXの加速と働き方に対する多様性の容認、そして人々の意識が重要となる。住生活基本計画には、ほかにも前編で触れたセーフティネット登録住宅の活用を推進していくことや、空き家の多様な利活用の推進なども含まれている。
次ページ ▶︎ | 「マイホーム神話」の崩壊 テーマは「アフォーダブル住居」
「マイホーム神話」の崩壊 テーマは「アフォーダブル住居」
コロナの影響により、国民の日常生活の変化が、不動産・賃貸業界にも大きな影響を与えている。働き方の変化だけでなく、経済的不安もあり、高額なローンを組むことに不安を抱える若者たちも増えた。進学や就職で賃貸のワンルームマンションに一人暮らし、その後結婚し、子どもが赤ちゃんの頃までは賃貸でお金を貯めて、子どもの成長と共にローンを組みマイホームを購入。そして、子どもたちが大きくなり家を出て、夫婦で住み続ける……。持ち家があれば安心という「マイホーム神話」も崩壊に向かっているのだろうか。
「戦後の“人生60歳”モデルケースから、私たちの世代は80歳、これからの世代は人生100年と言われ、いままでのモデルケースではフィットしなくなってきました。寿命が長くなるということはその分費用もかかります。いままでのように、住宅に全資産をかけ莫大なローンを払い続けていく、ということは難しくなってきているのです」(長谷川氏)
そのときの状況に合わせて住居タイプを選ぶ、というような選択も増えていくであろう。賃貸住宅でも今後は、ファミリー用物件の需要が増える可能性もある。
「いままでの賃貸経営は、『物件に費用をあまりかけず短期間で投資資金を回収する』というビジネスモデルが主流でした。賃貸住宅でも長く住めるよい物件を作ること、いろいろな住み方を提供すること、コミュニティなども重視しつつ、住人が満足できる豊かな住環境にしていくことが課題です」(長谷川氏)
それは賃貸だけにとどまらない。
「既存住宅を安く購入し、自分好みにDIYしながらアフォーダブル住居(良質かつ高額すぎない余裕のある住居)に居住するというような選択肢もあるのでないでしょうか。既存住宅の活用も含め、アフォーダブルな住宅供給の取り組みも課題の一つです」(長谷川氏)
賃貸の家賃を、アフォーダブル住居の購入資金に充当することでローンの完済期間を短くし、修繕費などにも充てることができる。引っ越す、移住するという選択肢も増え、人生100年時代における資金計画、そしてライフスタイルの多様性にもフィットしていると言えよう。
“子どもが育つと広い家は必要がない” “老後は住居に広さや庭は求めないが、通院や生活がしやすい市街地のマンションがいい”という意見も多い。高齢化により、変わり始めていた“住まいに求めるもの”が、コロナ禍により加速し、変化していくことは間違いなさそうだ。
次ページ ▶︎ | 急速な高齢化が進むニュータウンなどの住宅団地
急速な高齢化が進むニュータウンなどの住宅団地
前編で触れた「ニュータウンや郊外の団地の高齢化」について、この問題の解決の糸口はみえているのだろうか。長谷川氏によると、現状さまざまな取り組みが行われているが、成功している事例としては2パターンあるという。一つは開発事業者であるデベロッパー主導のもの、もう一つは住民が主導のものである。それぞれのケースをみてみよう。
■関係事業者主導型
「開発事業者主導型」の住宅団地の再生は、該当住宅団地を興じた事業者が再生にも関わるケースである。
鉄道事業者が関わったケースでは、住宅団地の住人が減ることにより出勤や通学に電車を使わなくなったため、電鉄会社の収益にも打撃を与える結果になっている。加えて、住宅団地内にある商業施設の土地なども電鉄会社所有であることが多く、開発事業者である電鉄会社にとっても住宅団地再生は解決しなくてはならない大問題なのである。
そこで行われている取り組みとして、鉄道沿線の圏域ごとに、駅前と郊外の住宅団地の間で、ライフステージに応じた住み替えを促進させ住宅団地の再生を図っている。例えば、20代〜30代の若い世代はまず駅前の賃貸住宅に住み始め、30代の半ば頃になりマイホームを購入するとなったとき、郊外住宅団地の既存住宅を確保してもらう。そこに住み続けていくなかでリフォームをしたり、住宅団地のなかで住み替えをしながら60歳ぐらいまで郊外住宅団地に住み続けてもらう。それ以上の年齢になり、車での生活が難しくなると郊外は不便になるため、駅前にサービス付き高齢者向け住宅などを整備して、そこに住み替えてもらう。また、そのあいた住宅を子育て世代に……という長期間にわたってサイクルを形成しようというものである。
この場合、既存住宅の流通が要となるので、戸建て住宅でも長期の維持・保全計画の作成を支援し、価値を維持できるようにしなくてはならない。住宅の状態を専門家が診断するインスペクションの体制を充実させたり、地元の金融機関と連携して将来のリフォーム資金の積立て制度を検討するなどの取り組みも行われている。
■地域住民主体型
自治会が主体となって、行政や関係事業者に積極的に働きかけ、関係機関と連携した取り組みを行っているケースである。
東京郊外の高齢化率が約50%を占める住宅団地では、自治会が行政などに積極的に働きかけてサポートを取り付けることで再生へ動き出している。高齢者向けの活動、子ども向けの活動、防犯活動、買い物環境の整備(移動販売の導入)、地域交流活動、ショッピングセンター地区の再生検討という6つの取り組みに分け、地域住民が自分たちでできることと、自治体や専門家と共に取り組むべきことを区別し、自治体などと協働すべきところは、積極的な働きかけを行いさまざまなサポートを取りつけて活動しているという。
また、自治会自らが建設工事を発注したり、自動車を購入・保有したりできるよう、認可地縁法人(自治会、町内会等広く地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織のなかでも、地方自治法などに定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たものを指す)を取得しているということも新しい動きである。
埼玉県にある高齢化率43%に及ぶ住宅団地は、非常に急勾配な北斜面地に開発された住宅団地であり、現在は30分に1本しか電車が通っていない状態である。かつては大手のスーパーがあったが撤退し、日常の生活を賄う商業機能がこの住宅団地内にはない状態である。
この住宅団地では自治会が主体となりながら、再生活動のコーディネーターとして大学を巻き込み、NPOや事業者などのさまざまなプレイヤーと連携しながら再生に取り組んでいる。再生の取り組みのほかにも、日常の買い物や通院など団地外への移送サービスを、自治会と居住者が立ち上げたNPOの2つで協力して行っている。
注目すべき新しい取り組みとして、活動の主体を担っている自治会では、役員の任期により交代してしまうと活動に限界があることから、自治会組織とは別に、再生を担う組織として新たにNPOの組織化を始めていることだ。これをきっかけに、自治会から徐々に担い手を地域住民主導のNPO組織へとシフトし、自治会の限界を超えて再生を進めていく流れだ。
いずれにせよ、地域住民が地域への関心をいかに高めていけるかが、住宅団地の再生を考えていくうえで重要であり、居住者自らが再生を自分たちの問題として捉え、危機感をもって主体的に取り組んでいかなければ、持続的な再生にはつながらない。そして、自分たちだけで解決を目指すのではなく、行政、NPO、企業、大学などとつながり、共に取り組まなければ解決できる問題ではないことは間違いないようである。
住人・マンションともに「高齢化」
団地だけでなく、老朽化したマンションも多くの問題を抱えている。高度成長期に勢いよく建てられ続けたマンションも、いまや築年の古い“老朽化マンション”となり、膨大な数に上ることが分かった。
築後30、40、50年超の分譲マンション戸数

出典/国土交通省「築後30,40,50年超の分譲マンション戸数」を基に作成
このデータによれば、20年末時点で築40年超のマンションは103.3万戸。それが10年後には、倍以上の約231.9万戸に。さらに10年後は、4倍以上の約404.6万戸にまでなると推計されている。マンションは戸建てより外壁の剥落などの危険性や、費用の掛かる大規模修繕が生じるうえに、個人の意見で修繕や建て替えなどを決定できないマンションも多い。さらに、所有者が高齢化し空き家も増えていくことになれば、修繕、建て替えの意見がまとまらず、再生が進まなくなる。
「成熟した良好な環境を安全に、適切に維持管理していくことを大前提として、どのように高齢化、廃墟化させず再生していくかという課題に時間的猶予はなく、早急に取り組まなくてはなりません」(長谷川氏)
「平成30年マンション総合調査」によると、ストック総数の34.8%が、修繕積立金が不足しているとされる。それだけでなく、住民が高齢化して管理組合の担い手不足の問題、組合が私物化されて修繕計画が破綻しているケースも多いという。さらに、当初計画されていた長期修繕計画が遅延され、計画の見直しをしなくてはならないケースもある。
このような状況で、長期間にわたり手入れがなされていない老朽化マンションは、“時代遅れ”な設計や設備が受け入れられず空き家化が進行し、外壁の剥離や落下事故という居住者だけでなく周辺住民にまで及ぶ危険性をはらみ、もはや修繕だけでは解決できず、最終的な選択肢は「建て替え一択」となってしまうのだという。
新耐震基準に満たないマンションもいまだに多く、高齢化が急速に進むマンションのストック数の危険性を問題視した国は、新たに「管理体制の適正化や除去認定の権限、建築法規の緩和権限」という2つの側面から地方公共団体に権限を付与した。それが、20年6月に成立・公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」である。

出典/国土交通省「マンション建替円滑化法の改正概要」を基に作成
マンション建て替え事業のより円滑な運用を目的として、14年から円滑化法の一部が改正され、これまでマンションの解体・敷地売却には、区分所有者全員の合意が必要だったがものが、5分の4以上の合意があればマンション建替法で手続きできるように緩和された。さらに19年からは、「敷地売却」という敷地を不動産会社などに売却し、住民はその代金を元手に建て替えられたマンションに再入居したり、別の住居に引っ越したりする仕組みも選べるようになった。
そして「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」により、耐震性不足だけでなく、「外壁剥離等により危険を生ずるおそれがあるマンション等」「バリアフリー性能が確保されていないマンション等」の危険性が高いマンションなどについても、5分の4以上の同意によりマンション敷地を売却できるようになった。
「少子高齢化で世帯数は減っていくので、建て替えより敷地売却への流れになるでしょう」(長谷川氏)
本年度も国交省では改正法の適用範囲をさらに見直し、実際の事案に柔軟に対応することを目的として有識者による検討会を開催。猶予を許さない老朽化マンションに対する法整備を進めている。
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。