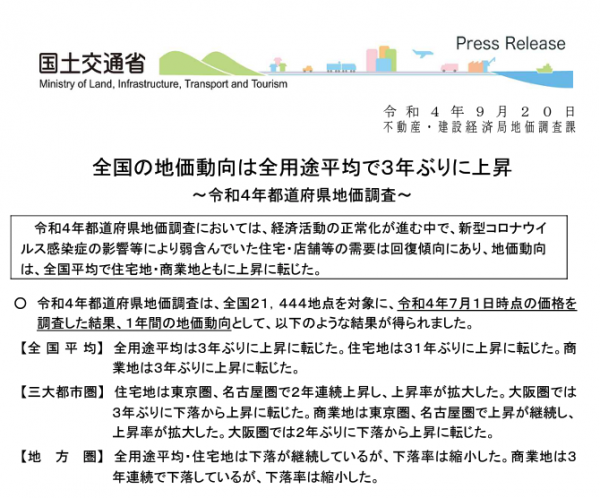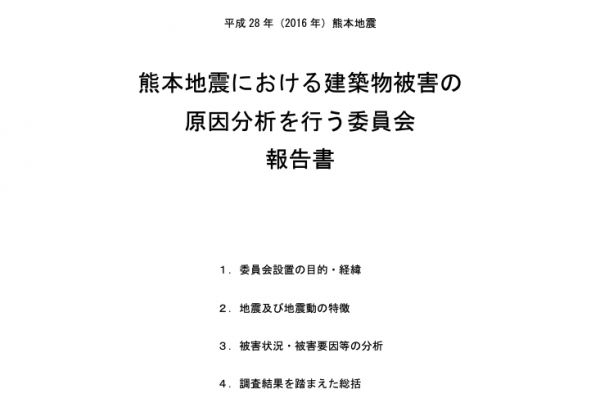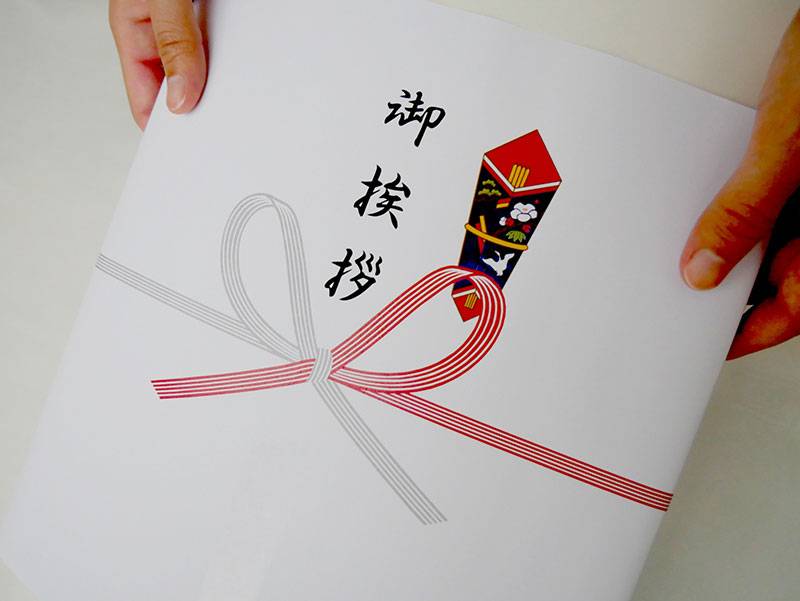衝撃のラスト12分。映画『FAKE』を観たあなたは何を感じ、何を思うのか?

2016/06/09

(C)2016「Fake」製作委員会
ドキュメンタリーとは何なのか?
前回に引き続き特別編として、現在公開中の映画『FAKE』を監督した森達也氏のインタビューをお送りします。
およそ2年前の2014年2月、一大スキャンダルとして日本中の注目を集めた全聾の作曲家、佐村河内守氏の「ゴースト騒動」をご記憶でしょうか? 映画『FAKE』は、その佐村河内氏の「その後」を撮ったドキュメンタリーです。
★★★『FAKE』公式サイト: http://www.fakemovie.jp/
後編となる今回は、映画の内容についてはもちろん、ドキュメンタリーとは何なのか、ジャーナリズムとはどう違うのか、森監督の創作への思いや世界観などもお聞きしました。
ドキュメンタリーの「演出」とは?
——『FAKE』というタイトルのせいもあって、仕込みだらけのやらせに近い映画だと思っている人もいるということでしたが、ドキュメンタリーには演出さえも許されないものだと思い込んでいる人もいるようです。
森: ドキュメンタリーは化学の実験に似ています。フラスコのなかに被写体を入れて、火であぶったりゆすったり、さまざまな刺激を加えます。つまり、被写体を挑発し、誘導する。それがドキュメンタリーの「演出」です。ときには撮影する側もフラスコのなかに入って、逆に被写体から刺激されることもあります。ドキュメンタリーは表現であり、作品ですから必ず撮る人の意図が入るわけで、それがなければ、ドキュメンタリーではなく、監視カメラの映像です。
——監督自らが被写体に働きかけるのですね。
森: そうした働きかけは、あらかじめこれを仕掛けてやろうと決めておいたこともあれば、現場でカメラを回しながら思わずつぶやいてしまったり、問いかけてしまったりすることもあります。
ただ、始めから狙って仕組んだことは面白くないんです。ドキュメンタリーに携わる人たちは、「ドキュメンタリーの神が降りてきた」という言い方をするんですが、現場でたまたま起こったことのほうが断然面白い。
事実、映画のなかに使っているのは後者のほうが圧倒的に多いです。ラストシーンで僕は「いいシーンが撮れました」と口にしているのだけれど、あれは思わず出てきた言葉ですし、実際にいいシーンが撮れたと思っています。

(C)2016「Fake」製作委員会
映像は関節話法、活字は直接話法
——監督は、ノンフィクションなど文章を書くお仕事もされていますが、映像と活字をどのように使い分けられているのでしょうか?
森: いまは映像だとか、いまは活字だとか無理に区分けしている時期もありましたが、いまはもうどちらでもいいと思っています。映像向きの素材と活字向きの素材があるので、素材によって使い分ければいい。
ただ、映像はやっぱり間接話法なんです。そういう意味ではやっていて楽しいのは映像のほうかもしれない。やはり、直接話法はあまり好きじゃないですから。僕は、佐村河内さんについては本を書かなかったし、これから書く気はありません。活字はどうしても直接話法になってしまう。もちろん、それが効果的な素材もあるけれど、今回については直接話法を使いたくなかった。
撮影中に予期せぬことが起こるから面白い
——映像と活字では、それを観る人、読む人に与える影響力にどんな違いがあるとお考えですか?
森: たとえば「ここにテーブルがある」という文章があったとしたら、そのテーブルはどんな大きさかとか、何色なのか、上には何が乗っているのかとか、読みながら考えなければなりません。でも、映像は実際にテーブルが見える。そう考えると、想像力が求められる領域は活字のほうがはるかに大きい。
でも、一方で活字が想像力を狭めてしまうこともある。たとえば、「口元を歪めた」という書き方をすれば、読み手はネガティブな印象を受けるはずです。あるいは、「口元が下がった」とか「口元が上がった」とか、どんな書き方をしても絶対に何らかの意味を示してしまう。でも、映像はダイレクトに被写体の表情を映すことができるからこそ、観ている側は「いま何を思っているのだろう」と考えさせられます。つまり、映像は作用する力が大きいんです。
ただし、つくっていく過程についていえば、映像も活字も基本的には同じで、結局、どちらも現実にいかに揺さぶられるかが重要だと思います。映像であれば撮影中、活字であれば取材中に、予期せぬことが起こるから面白い。
たとえば『A』の不当逮捕のシーン、公安がわざと転んで、オウム信者を公務執行妨害で逮捕する場面があるのだけれど、あんなシーンは、もしフィクションをつくるとなっても思いつくことさえできないはずです。活字でいえば、『クォン・デーもう一人のラストエンペラー』。僕はあの本で、最後に自分の目論見をひっくり返されてしまう。そんなふうに撮りながら、書きながら、現実に翻弄されないと面白いものはつくれません。

(C)2016「Fake」製作委員会
僕が撮ったのは映画。ジャーナリズムではない
——監督の作品である『A』『A2』、そして今回の『FAKE』も、マスメディアとはまったく違う視点で撮られています。「タブーに挑む」と形容されることが多いですが、ご自身ではあまりそういう意識は持たれてないそうですね。
森: たまたま興味のあることを撮った結果、タブーだっただけです。ただ、やっぱり隠されているものは見たいと思うし、知りたいと思う。そうすると当然、タブーに抵触することは多くなるんでしょうね。
僕の作品は要するにアンチなんです。いまのこの状況に対してのアンチ。『A』も『A2』も『FAKE』もそうですし、活字も基本的にそうだと思う。いまの状況でいいと思ったら、僕は撮ることも書くこともしません。そういう意味では、社会に歯向かっているわけですから、タブーだといわれることは当たり前かもしれません。逆に、そういわれなかったら、自分の視点が間違っていたんじゃないかと心配になってしまう。メディア批判が多くなることは、メディアは社会の合わせ鏡だと思っているからです。社会を射程に置かない作品では意味がない。
——「誰にも言わないでください。衝撃のラスト12分間。」というコピーの通り、衝撃的なラストシーンでした。観る人がいちばん知りたいであろうことを明らかにしないまま終わってしまいますが、監督は答えをご存知なんですよね?
森: もちろん知っています。でも言いません。観た人がそれぞれ解釈してくれればいい。答えがわからないことを不満に思う人がいるかもしれないけれど、それはある意味では狙い通りです。
答えを明らかにするために今回の映画を撮ったわけではありません。もう一度言うけれど、それではジャーナリズムになってしまう。これは映画です。視点や解釈はそれこそ無数にあっていい。観た人の自由です。さまざまな視点と解釈があるからこそ、この世界は自由で豊かで素晴らしいのです。
映画『FAKE』、公開情報
■『FAKE』 監督・森達也
渋谷・ユーロスペース、横浜シネマジャック&ベティにて公開中、6/11(土)より大阪・第七藝術劇場ほか全国順次公開。 詳しくは公式ホームページ( http://www.fakemovie.jp/ )にて
■『A2 完全版』 監督・森達也
6月18日(土)〜24日(金)連日21:00、7月9日(土)〜15日(金)連日21:00より渋谷ユーロスペースにてレイトショー
今回のこの人は…

森達也(もり・たつや)
1956年広島県生まれ。オウム真理教信者たちの日常を追った『A』(98年)、『A2』(01年)、フジテレビ「NONFIX」枠では『「放送禁止歌」〜歌っているのは誰? 規制しているのは誰?〜』などでタブー視されていたテーマに挑む。『「A」撮影日誌』(現代書館)、『職業欄はエスパー』(角川書店)など著作も多数。近刊では初の長編小説作品『チャンキ』(新潮社)がある。
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。