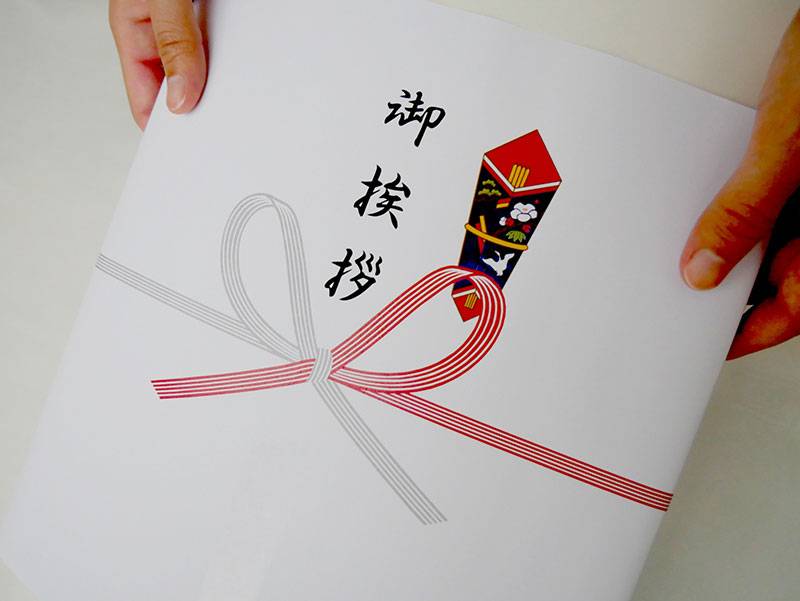契約社員でも住宅ローンは借りられる? おすすめの住宅ローンは?

2017/10/19
契約社員は住宅ローンを借りられる?
改めて申し上げるまでもないことですが、住宅ローンは“お金の貸し借り”です。そのため金融機関は、借り入れを申し込んだ人の返済能力の有無を見きわめて(審査して)、貸し付けても問題ないかどうかを判断します。
住宅ローンは金額が大きく、返済が長期に渡るため、審査の際には、「収入の安定性」が重視されることとなります。そのため、より雇用が安定している正社員のほうが審査は通りやすくなるのです。なかには最初から審査申し込み要件を「正社員のみ」と明記している金融機関も多くあります。
ですが、最近では雇用の多様化を受け、雇用形態が正社員でないというだけで申し込みができないという金融機関は、かつてに比べると減ってきているように感じます。
厚生労働省によると、平成9年には3812万人だった正社員は、平成25年の3294万人まで減少しています。一方、非正規の雇用者は、昭和59年の604万人から増加し、平成25年には1906万人となりました。
これには子育てを終えた主婦がパートやアルバイトなど非正規雇用で社会復帰している影響もあるようですが、社会全体で非正規雇用が増えているのは確かなことです。金融機関も、正社員だけを対象としていては顧客の絶対数が足りないという現状もあるかと推測します。
金融機関が審査で重視するのはどんなこと?
せっかく、申し込み条件が「契約社員でも可」という金融機関を見つけて審査を申し込んでも、肝心の審査が通らなければ意味がありません。申し込みをしたものの、結局、住宅ローンは借りられないということになってしまいます。
では、金融機関が審査で重視するのはどういった点でしょうか? 以下にポイントをあげてみましょう。
(1)雇用の安定
前述した通り、住宅ローンは大きな金額を長期間で返していくものです。そのため、金融機関は雇用が安定しているかどうかを重視します。
契約社員と一口に言っても、契約期間はそれぞれです。契約内容によって、数カ月~3年程度と、その契約期間には大きな差があります。同じ契約社員でも契約期間が長期、かつ契約の更新回数が多いほど安定性が高いといえるでしょう。
(2)年収
当然、収入は多いほうが借入時は有利です。契約社員は結果を出せば更新時に給与がアップする、実績よってボーナスが支給されるケースもありますが、そういった事例も好材料です。
(3)返済比率
返済比率は収入における返済金の割合のことですが、これは住宅ローンの借り入れだけでなく、マイカーローンや教育ローンなども含まれます。契約社員の方の場合、雇用形態の面で不利な分、住宅ローンを申し込む際には、ほかの借り入れは清算しておいて、できるだけ返済比率を引き下げておきたいところです。
返済比率の目安は、通常25~30%程度とされていますが、契約社員の方はより低く20%未満を目指すことをおすすめします。
(4)自己資金の有無
自己資金は当然、あったほうが有利です。自己資金があるということは、借入金額を抑えることや返済比率を低下させることにつながります。
また、自己資金があるということは、貯蓄のできる家計であることの証明になりますから、金融機関へも好印象を与えることができます。
ここでご説明した金融機関が重視するポイントは、対象が契約社員の方の場合に限りません。正社員の方が対象であっても、契約社員の方が対象であっても、住宅ローンの審査内容は同じです。ただ、一つひとつの審査の条件がより厳しくチェックされる、と考えるといいでしょう。
次ページ ▶︎ | 契約社員の申し込みを受け付けてくれる金融機関を見つけるには?
契約社員の申し込みを受け付けてくれる金融機関を見つけるには?
では、契約社員の方でも借りることができる、おすすめの住宅ローンとはどのようなものでしょうか。
まず確認しておきたいのは、「住宅ローンの申し込み条件」です。申し込み条件の中には通常、勤続年数の定めがあり、「勤続年数3年」などと記載されているのが一般的です。
ここで注意していただきたいのは、なかには「勤続3年以上の正社員」と明記されている場合もあるということです。もし「正社員」と書かれている場合は、その金融機関へのローン申し込みは見合わせましょう。
「契約社員も申し込み可能」と明記している金融機関が理想的ですが、数は多くありません。そもそも、雇用形態ごとの申し込み条件を公表していない金融機関が大半です。さらに、実際に問い合わせても「個別状況によります」と可否を教えてもらえないことが多いです。
申し込み要件が分からない場合、いきなり仮審査を申し込むのはリスクが高いです。少し遠回りになっても、審査の申し込みを考えている金融機関が実施している住宅ローン相談に足を運ぶなどして事前に動向を確かめましょう。
収入合算できる金融機関を選ぼう

(c) Monet – Fotolia
契約社員でも申し込み可能な金融機関を見つけたら、審査を有利にするために、利用を検討したいものがあります。
それは、「収入合算」です。収入合算とは、たとえば夫婦共働きの家庭など、複数の人に収入がある場合、それぞれの収入を合計し、世帯収入としてカウントして住宅ローンを借りることができるものです。通常は夫婦間の収入を合算します。
ただし、収入合算には制限があることが多いです。たとえば、夫がメインの債務者になる場合には、妻の収入は2分の1までしか合算できないとしている金融機関もあります。
金融機関によって対応が異なりますので、世帯収入がより多くなるように、収入合算の要件が緩い金融機関を選びたいところです。
次ページ ▶︎ | 【フラット35】は比較的審査が通りやすい
【フラット35】は比較的審査が通りやすい
契約社員でも申し込みを受け付けてくれる金融機関を選ぶのと同時に、どの住宅ローンを選ぶかも大切です。
住宅ローンの審査基準には「人的基準(人に対する審査)」と「物件基準(物件に対する審査)」の2種類があるのをご存知でしょうか?
全期間固定金利型の住宅ローンである【フラット35】の場合、物件に対する審査に重きを置いており、職業に関する制限は申し込み条件のなかにありません。【フラット35】は、国民に「質の良い」住宅を購入してもらおうという趣旨の制度だからです。そのため、民間金融機関の住宅ローンに比べると、契約社員であっても利用しやすいといえるでしょう。
ただし、【フラット35】の物件に対する審査は厳しく、面積や建築における一定基準を満たす必要があるので注意しましょう。
また、前述したように返済比率も低いほうが望ましいです。預貯金が少ない場合や、預貯金があっても手元に残しておきたい場合は、購入する住宅そのものを価格の低いものに変更するなど、見直しをしましょう。
見直しにあたっては、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家に相談するのもおすすめです。
非正規雇用でも住宅ローンの“借り換え”はできる?
さて、これまで住宅ローンを新規に借り入れする前提でお話してきましたが「借り換え」の場合どうなのでしょうか。
住宅ローンの金利が非常に低い水準にある今、借り換えをして金利の負担を抑えたいという人は少なくないと思いますが、契約社員であっても、住宅ローンの借り換えをすることは可能なのでしょうか。
借り換え先の金融機関にしてみれば、借り換えも新たな貸し出しになります。そのため、住宅ローンの借り換えであっても契約社員の場合は、審査に通る難易度が高いといえるでしょう。
ですが、すでに借り入れしている住宅ローンをきちんと返済し続けていれば、それも大きな信用になります。ですから、これまで返済を滞らせたことがないのであれば、ここでお話ししたポイントに留意しながら借り換えにトライしてみましょう。
派遣社員やアルバイトの場合は?
派遣社員の場合は、勤続年数が長くければ契約社員の場合と同様、借り入れできる可能性はゼロではありません。
ですが、アルバイトやパート勤務の場合、契約社員よりもさらに借り入れは難しくなると言わざるを得ません。雇用の不安定さももちろんですが、年収要件も高い壁になるからです。
一般的に、住宅ローンを組むためには、年収300万円程度が必要とされますが、時給で働くアルバイトやパートの場合、時給がかなり高くないと、年収要件を超えるのはむずかしいでしょう。勤続年数が長く、時給も高いといった条件を満たしている人以外は難しいと考えたほうがよいのではないかと思われます。
年収要件をクリアするためには、時給アップが必要ですが、その交渉は簡単ではないでしょう。雇用形態を契約社員へ変えてもらえないか、勤務先に相談してみてはいかがでしょうか。
これまで見てきたように、契約社員であっても、住宅ローンの借り入れはできないわけではありません。ただし、条件は厳しくなるため、金融機関選びを慎重にしつつ、自己資金の貯蓄をしておくなど、自身の家計環境を整えておきましょう。
情報提供元:アルヒマガジン( https://magazine.aruhi-corp.co.jp/ )
記事名:「契約社員でも住宅ローンは借りられる? おすすめの住宅ローンは?」( https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-0952/ )/
(元記事公開日 2017/05/26)
この記事を書いた人
ライフプラン応援事務所代表
ファイナンシャルプランナー(AFP)、住宅ローンアドバイザー。企業に属さない独立系FPとして、2013年ライフプラン応援事務所を立ち上げて以降、住宅相談を専門に扱う。マイホーム相談では保険見直し、教育費、退職後プランなど総合的な視点で資金計画、および返済計画を考案。相談業務のほか、セミナー講師、執筆業など情報発信、啓蒙活動にも力を入れている。 「自分の家計は自分で守る」をモットーに、丁寧でわかりやすい面談が好評。 また、給付金や控除など、消費者のための制度を調べるのが得意で、「ここが使いにくい」「誰のための制度なのか」などとケチをつけるのが好き。