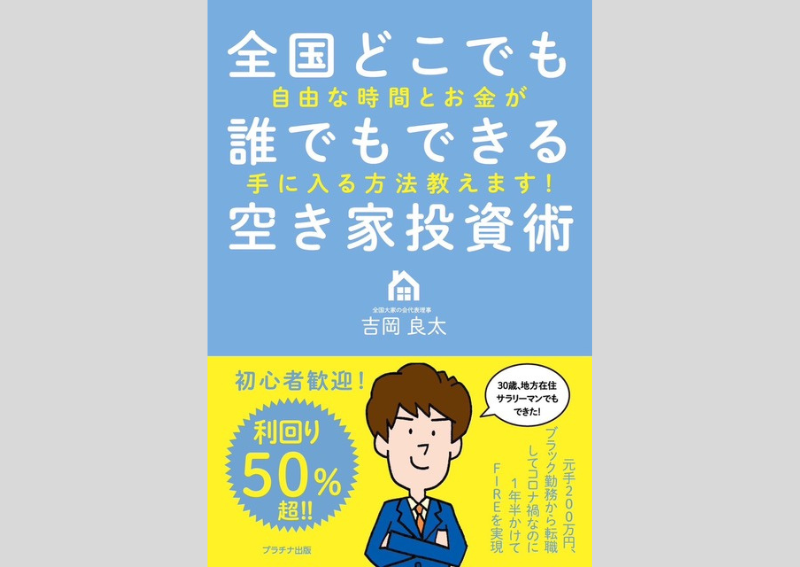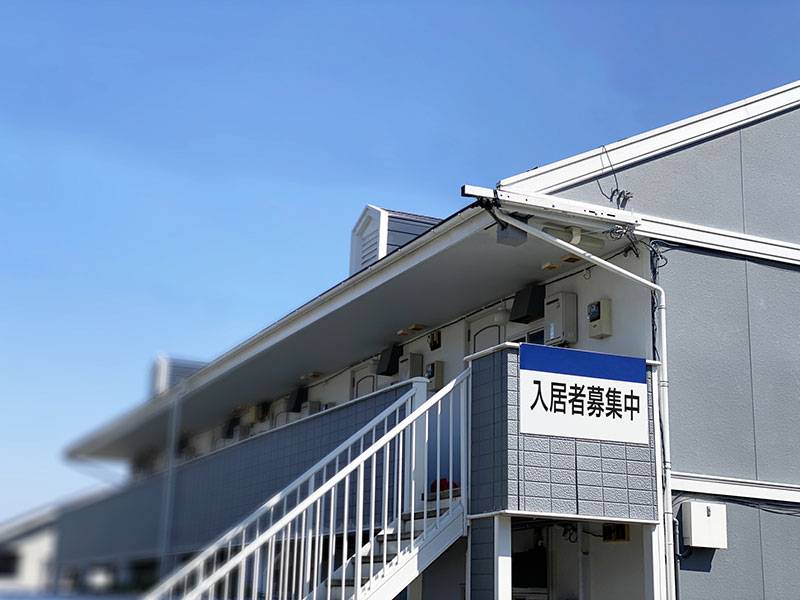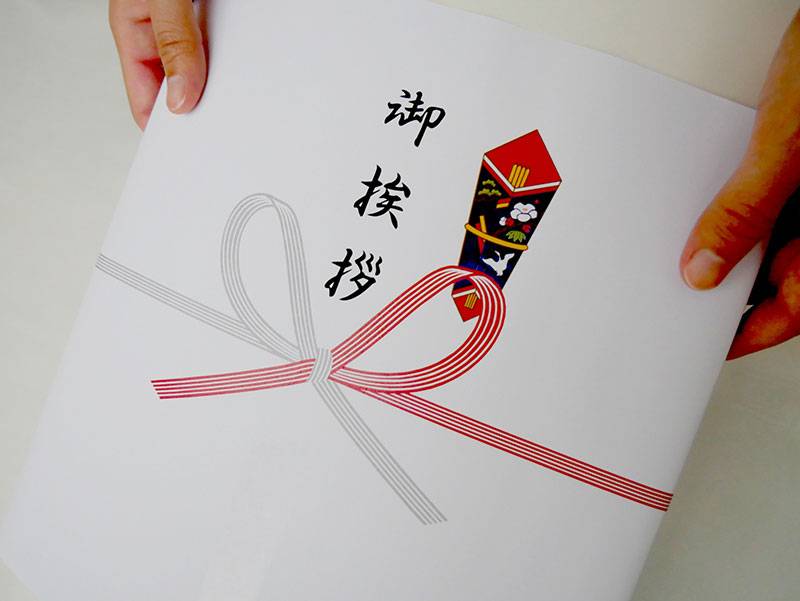入居者さんに水害への心構えの呼びかけを!

2020/01/28
昨年(2019年)10月に日本を襲い、各地に浸水被害をおよぼした台風19号。報道によれば、その後専門家の調査などから、
・21人が建物の浸水によって死亡
・半数以上が2階建ての1階で被害に遭っている
そんな状況が判明してきています。特に後者にご注目ください。場所は2階建ての1階です。平屋でもないのに、なぜこれら犠牲となった皆さんは、すぐに階段をのぼり、2階へ逃げなかったのでしょうか?
理由のひとつは、おそらく年齢です。犠牲となった方の中には、ご高齢の皆さんが多いとのこと(7割以上)。なので、体力に衰えもあっただろうとはいえ、それにしても…。調査の結果、どうやら家具や畳が2階への避難を妨げたのではないかと見られています。
これらは、使われている素材や状況によっては水に浮くのです。1階が浸水し、水に浮き始めた家具や畳に行く手を遮られ、動きが取れずにいるうちに、水かさがどんどん増してきて、逃げる機会を失った様子が想像できるということです。
さて、賃貸住宅です。賃貸住宅の場合、水害に対し、多くがある脆弱な特徴を持っています。それは建物が持つものではありません。住人の皆さんが持つものです。お気付きになりますでしょうか?
答えは、情報と知識です。彼らの多くが、物件の建つ地域の地理などに詳しくありません。ふるさとを離れ、遠くから越して来たなど、周辺の地理をまるで知らない入居者さんが、賃貸住宅には数多く住んでいらっしゃいます。
そのため、住み始めて2年、3年。それでも、駅と買い物に向かう道路の周り以外はほとんど歩いたこともなく、「すぐ近くに川があるなんて知らなかった!」そんな方も大勢いらっしゃいます。
そこで、洪水被害が予測される地域に物件をお持ちのオーナーさんへお願いです。入居者さんへ、水害リスクへの心構えをぜひとも呼びかけてあげてください。そのためには、まず、オーナーさんご自身が情報収集です。地元自治体のウェブサイトを早速開いてみてください。
防災関連のページを探します。見つかれば、そこにはハザードマップや過去に水害があった場合はその位置や被害状況、さらには自治体が行う避難勧告等の発令基準、避難所の位置といった、各種の情報が網羅されているはずです。
それらをオーナーさんもしっかりと把握したうえで、プリントアウトするなどして、入居者さんに伝えてください。なぜならば、われわれ賃貸住宅オーナーには、賃料と引き換えに、入居者さんへ安全で健康に暮らせる住まいを提供する義務があります。
もちろん、建物がその目的に沿っていることも大事ですが、災害時に命を守ることにつながる情報をあらかじめ提供しておくことも、間違いなくそのための正しいスタンスです。また、ある意味都合のよい話になりますが、経営上のリスクヘッジとしてもこのことは重要です。
建物内で被災死した人が出ることで、物件を事故物件としないためにも、入居者さんにはぜひしっかりと生き延びてもらわなければなりません。洪水災害を想定するうえで、入居者さんに必ず把握しておいてほしい、大事な情報を以下に掲げます。
まずは、「予測される浸水域とその深さ」です。家具や畳が水に浮き、避難を妨げるといった状況は、水の深さが1メートル程度でもすでに生じてきます。さらに、2メートルの浸水が予測されている場所でそれが現実となれば、1階の部屋の多くは天井近くまで水没します。
そのため、とくに1階に住まれている方には、「早めの避難をしないとあっという間に逃げ道が無くなる!」このことを躊躇なく伝えておくことが肝心です。なお、自治体のハザードマップには、もしかするとこんな記述があるかもしれません。
「このマップは、100年に1度程度の確率で発生する規模の大雨により○○川が氾濫した場合を想定したものです」
こうした記述は、われわれを惑わせます。100年に1度の大雨は、100年後に降る雨ではないのです。近年、気候変動が著しい中、まさに来年の雨、今年の次の雨こそがそれなのかもしれない、といった心構えがとても重要です。
次に、「避難場所の位置・名称」などの情報、さらには、「避難場所および物件周辺の地理」です。賃貸住宅の入居者さんは、さきほどもふれたとおり、住まい周辺の地理に疎い傾向があります。平常時、あらかじめ避難場所を訪れてみることも、ぜひ勧めてあげてください。
さらに、「情報収集の方法」です。洪水は、突然やってくる地震と違い、多くの場合予測が可能です。自治体のメール配信サービスやSNSアカウントを案内し、これにアドレスを登録したり、フォローしておいたりするよう、入居者さんに勧めてください。
また、聴き取りにくいことが多い防災行政無線ですが、多くの自治体が、放送内容を電話で聴けるサービスも設けています。インターネットを使いこなせない入居者さんがいらっしゃる場合は、こうした情報収集の方法があることも伝えてあげてください。
逆に、ネットだけに頼りがちな若い世代の皆さんには、携帯ラジオの備えも呼びかけてあげるとよいでしょう。
そして、「情報の内容」です。自治体が発する避難指示、勧告等の種類と、それらが発令された際は何をすべきか、それぞれの内容を入居者さんにしっかりと理解してもらってください。
以上。いわゆる地主さんも多い賃貸オーナーの場合、地元の地理に詳しく、ご近所の皆さんとのつながりも豊富な中で暮らされている方が比較的多いはずです。
一方、入居者さんの多くはそうではありません。会社へ通う電車が走る沿線の街として、たまたま偶然そこに住むことになっただけ…。住んでいる建物の周囲をどれだけ見渡しても、知り合いなどひとりもおらず、孤独な状態にあるといった方も決して少なくありません。
そんな彼らが災害に直面するとき、オーナーさんの助けはとても重要です。
(文/朝倉継道 画像/123RF)
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。